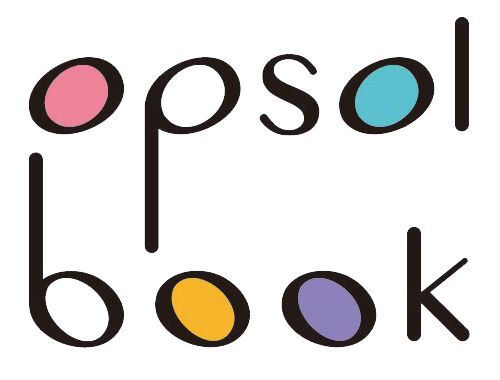【第3回ハナショウブ小説賞】最終結果発表!
第3回ハナショウブ小説賞 受賞作品
このたびは、第3回ハナショウブ小説賞にご応募いただきありがとうございました。
受賞作は下記のとおり決定いたしました。
opsol部門
【大賞】
該当作品なし
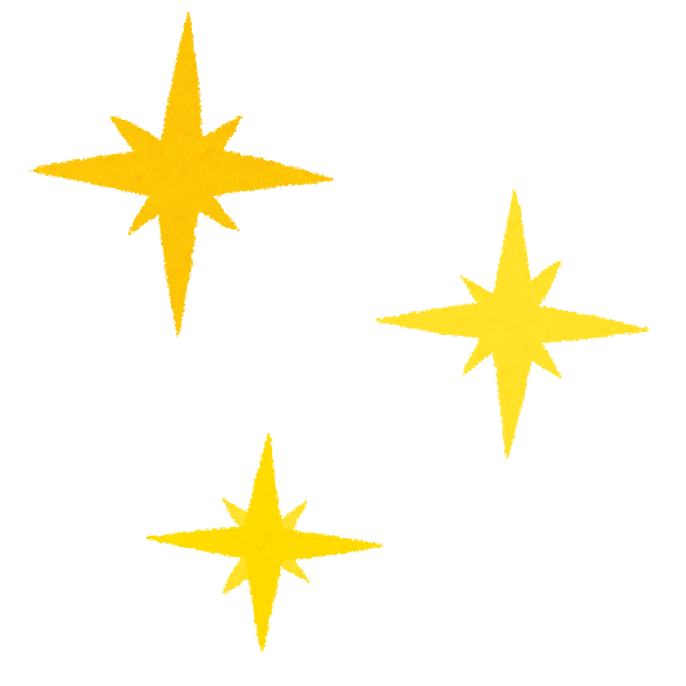 【金賞】賞金10万円
【金賞】賞金10万円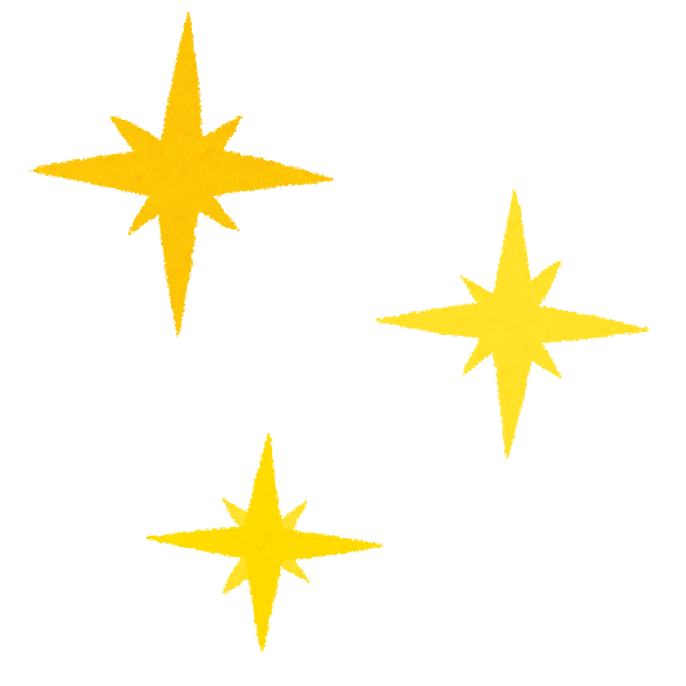
『生を紡ぐ』染夜美月
【銀賞】
該当作品なし
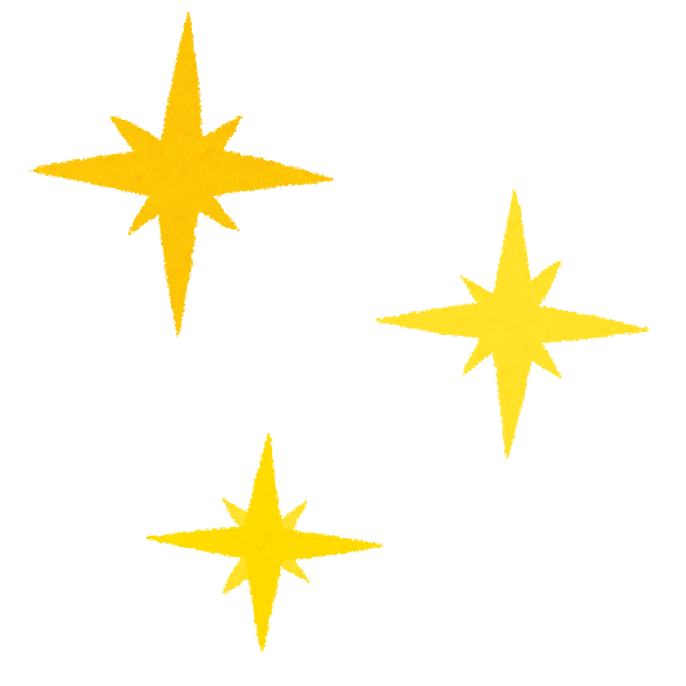 【opsol book賞】賞金1万円
【opsol book賞】賞金1万円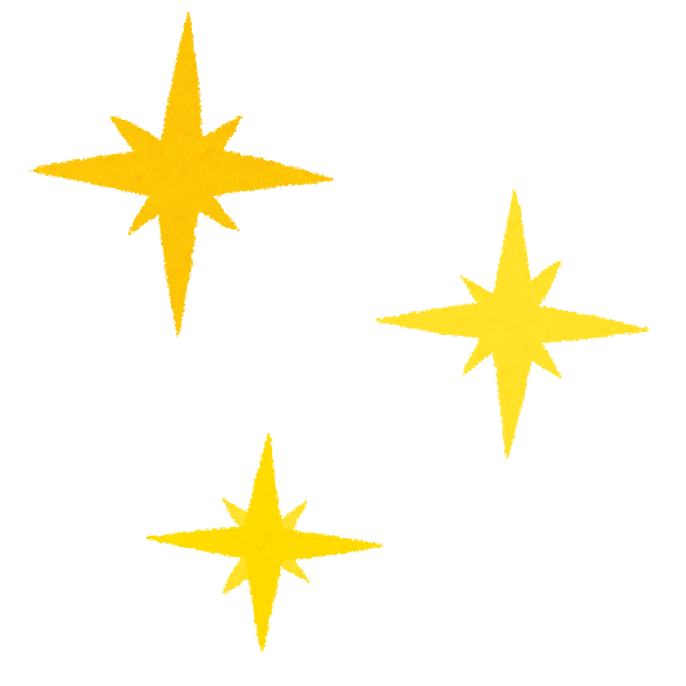
『あしたに一歩。』南木野ましろ
テーマ部門
【大賞】
該当作品なし
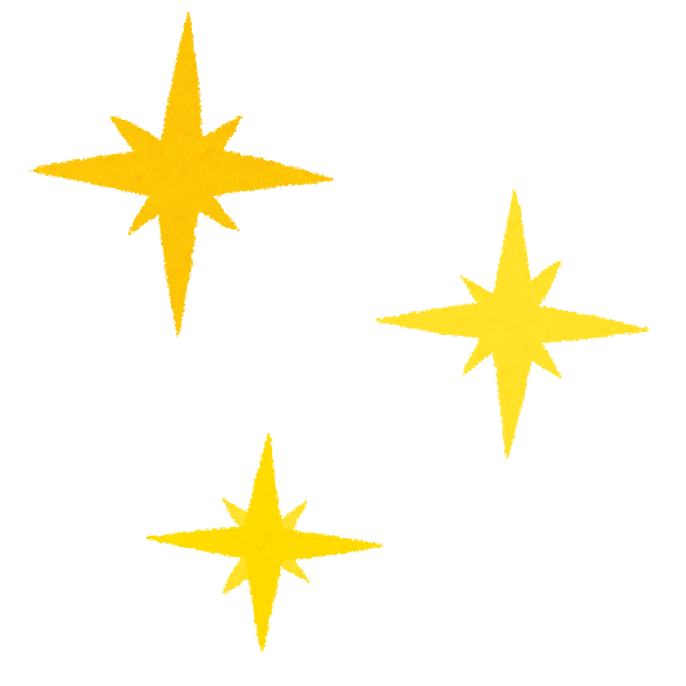 【金賞】賞金10万円
【金賞】賞金10万円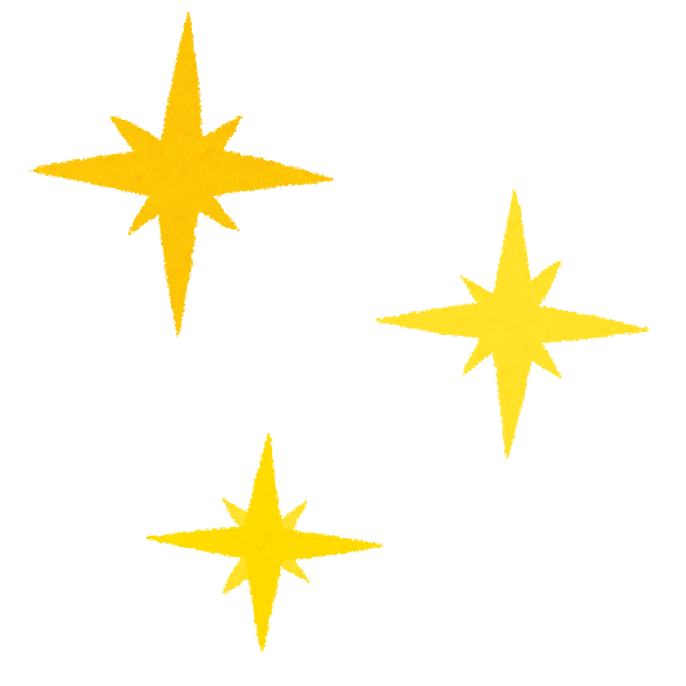
『母の思惑』南木野ましろ
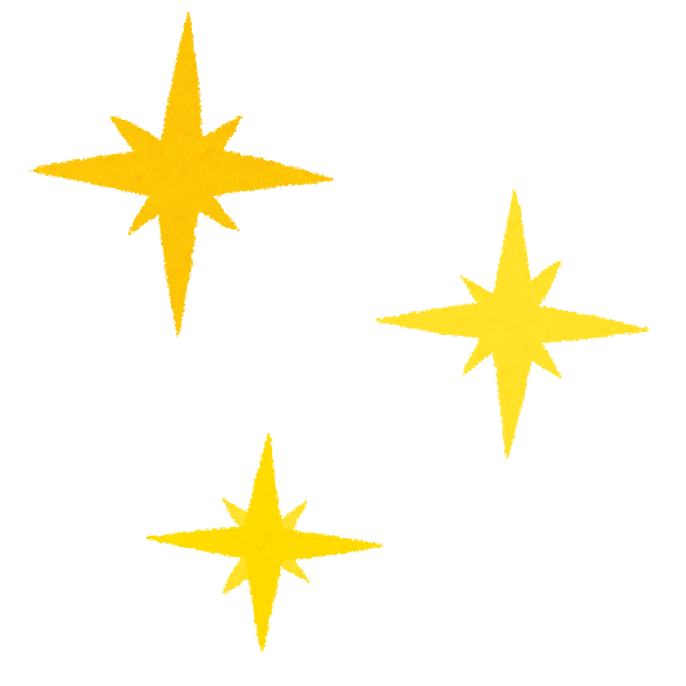 【銀賞】賞金5万円
【銀賞】賞金5万円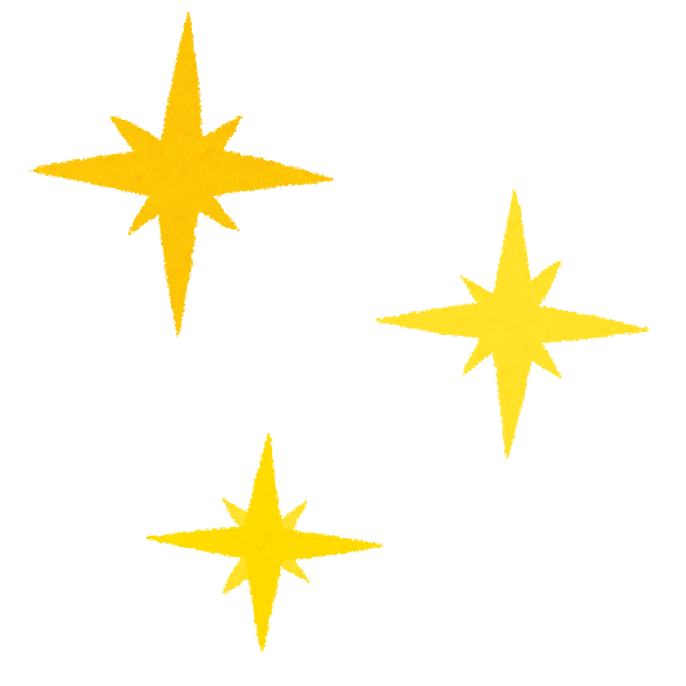
『二通の手紙』のがみなみ
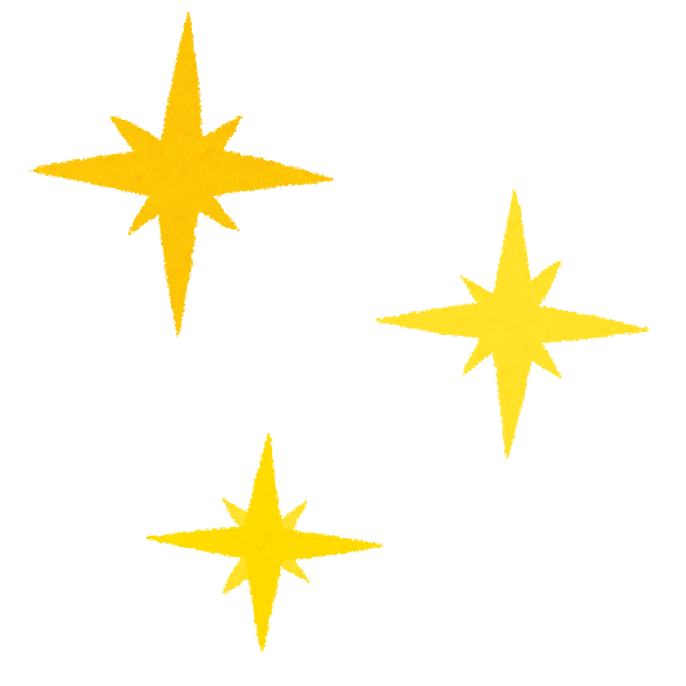 【opsol book賞】賞金1万円
【opsol book賞】賞金1万円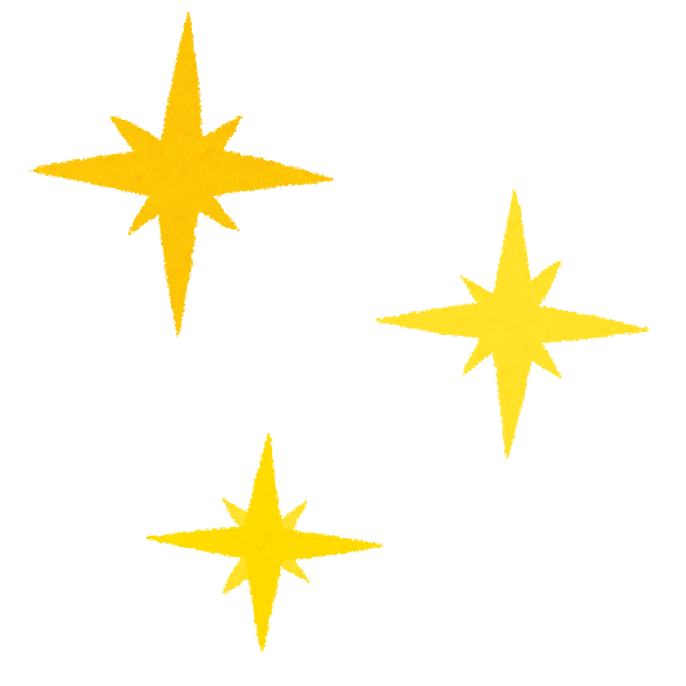
『文車』藍田陽彦
エッセイ部門
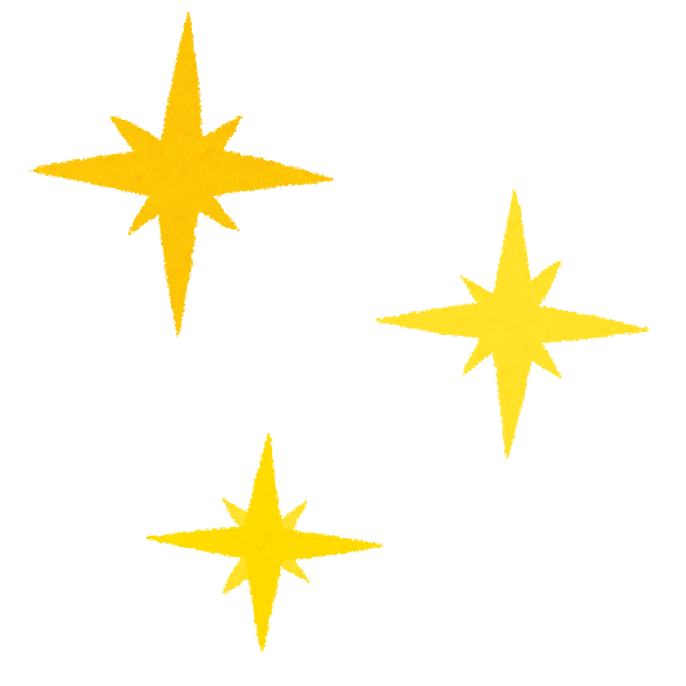 【入選】図書カード5,000円分
【入選】図書カード5,000円分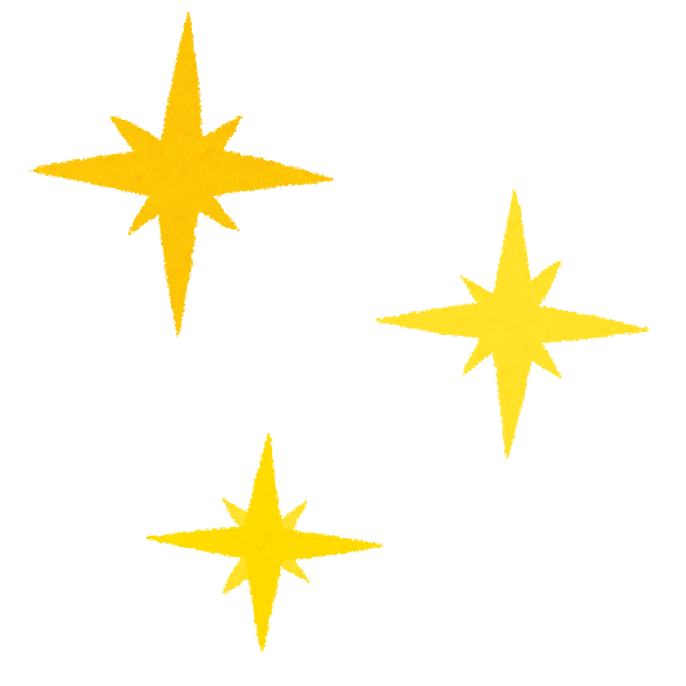
*入選10作品 順不同
『医師が深刻な症状で病院にかかって気づいたこと』吉村史年
『悲しい背中』おは
『グリーンのアイシャドウ』石川莉緒
『車椅子のカラヤン』野間栄子
『桜道』高鳥珠代
『障がい者の就労支援』北乃宙
『新人カラスの発声練習』秋田柴子
『食べてただいま』大島絆
『小さなヒマワリの思い出』空滝大地
『我が家の灯』杉本あずさ
選評(opsol部門・テーマ部門)
選考委員
鈴木 征浩【opsol株式会社 代表取締役社長 opsol book代表】
宮川 和夫【装丁家(宮川和夫事務所)】*opsol部門・エッセイ部門のみ
opsol book編集部
◆opsol部門 金賞『生を紡ぐ』染夜美月
【あらすじ】
葛藤を抱える者たちが繋ぐ、命の物語。
緩和ケア認定看護師の資格を取るために、東井大学病院に勤務地を移すことにした看護師の久遠麻衣は、勤務日初日に訪れた海辺で天野美鳥に出会う。彼女は、麻衣が配属される外科病棟の看護師だった。感受性が強く、患者や家族と共に涙を流す美鳥と、プロとして白衣姿では絶対に涙を流さない麻衣。真逆の看護観を持ちながら、プライベートの時間の殆どを一緒に過ごす二人だったが、一人の入院患者の死をきっかけに、麻衣は少しずつ美鳥の様子に違和感を覚えるようになり……(『夏の轍』)。
東井大学病院付属看護学校の学生である立花は、担当患者の大島さんに挨拶するも、不愛想な態度を取られてしまう。全く話を聞いてもらえないことに悩み、指導担当の看護師・植田に相談に向かうが、植田は立花の言葉を無視し、更には心無い言葉まで言い放つ。見かねた麻衣が植田を咎める場面に遭遇した立花は、そこで植田の理不尽な態度にも理由があることを知る。もしかして、大島さんの態度にも何か理由があるのだろうか。そう考えた立花は、大島さんと向き合うことを決意する(『孵化』)。
看護師、看護学生、病棟清掃員――6つの物語が交錯するオムニバス医療小説。
【鈴木 征浩】
それぞれの主人公たる看護師や人物の目を通して語られる物語に、著者が看護や医療というものに非常に真剣に向き合っていることが感じられる作品で、ひとつの病院・病棟にはたくさんの想いを持った職員達が関わっているのだということ、そして、患者も職員も、その数だけ代替性のないストーリーを抱えているのだということが良く表現されていました。
だからこそ、一部の設定やスポットを当てる方向に違和感を感じずにいられなかったことが悔やまれます。本作においては、現実離れした何かを描くのであれば敢えてリアリティあるものを描き、その上でその向こう側まで辿り着いてもらいたい、と感じました。
展開が駆け足気味に感じられるところはありますが、全体を通じてメッセージ性が高く、力が溢れている作品です。看護とは、病院で働くとは、という根源的な問に向き合った著者の思いが溢れている作品で、さらなるブラッシュアップを経れば、より素晴らしい作品になるものと思います。
【宮川 和夫】
現役の看護師ということで、医療現場がとてもリアルで丁寧に書かれています。またそれが説明的すぎずほどよく、全体的に読み応えがありました。
ひとつ残念なのは、1章で物語のキーを握る「天野美鳥」の描写が希薄すぎて実在感を感じられないことでした。
2章から後がよいだけに、天野美鳥を実体のある人として描き、最終章で第1章での久遠麻衣と天野美鳥の関係性を回収しつつ、麻衣の看護師としての葛藤と成長を描いて欲しかった。そうすればこの作品はさらに素晴らしいものになったと思います。
◆opsol部門 opsol book賞『あしたに一歩。』南木野ましろ
【あらすじ】
あの日握り返した武骨な手は、俺を未来へと導いた。
サッカーでスポーツ推薦をもらうため、志望高校が開催するセレクションに参加した中学三年生の樹生は、その日の帰りに交通事故に遭い、右足を失った。唯一の取柄だったサッカーも、思い描いていた未来も失い、喪失感と不安、絶望に苛まれ自虐的になっていた樹生は、入院先の病院で義肢装具士の古谷と出会う。
古谷は、これまで出会った大人とは違い、豪放磊落で傍若無人な男だった。死んだ方がマシだと言い放つ樹生に対し、古谷は荒々しい方法で樹生の本音を引き出す。容赦ない現実とその乗り越え方、義足を履く意義を教えられた樹生は、どこか型破りな古谷を少しずつ信頼し始めていく。
前を向くことを決め、リハビリに励んでいたある日、院内でひとつの噂を耳にする。その噂がきっかけで、いつも心強い言葉をくれる古谷もまた、過去に捕われ、苦しみを背負っているのだと知り……。
【鈴木 征浩】
サッカーの道を志す少年が交通事故に遭い片足を失い、義足が必要になったことをきっかけに始まった義肢装具士との交流の物語で、ストーリー展開的には、両者の交流が主人公の心だけでなく義肢装具士のそれの救いにつながっていく、というある種王道的なもので、それ自体は決して悪いとは感じません。しかしながら、全体を通じて様々な要素に「軽さ」を感じずにいられなかったことが非常に残念でした。
未来に大きな夢を描くことができる中学三年生で、サッカーの道を志す少年が片足を失うとは、どういうことか? 物語の根幹であり絶対的な存在である主人公が向き合わざるを得ない現実に、その心に、向き合うことで、はじめて意義が生まれる物語だと思います。また、それがあるからこそ、他の要素にも色が加えられていく物語だとも思います。
主人公に、登場人物に、もっともっと真剣に向き合ってほしい、と強く思いました。
【宮川 和夫】
サッカーの才能があり、スポーツ推薦で高校へ行こうという少年が、交通事故で片足を失ったときの絶望はいかばかりでしょう。まずその「絶望」を描かずして物語は始まらないと思いますが、その描き方が淡泊すぎるように思いました。また、彼の新しい「足」を作るべく義肢装具士が出てきますが、この人物を描くエピソードの一つが同性愛者である必然性が見当たらないことも気になりました。少年と義肢装具士のバディ感、会話のテンポの良さや物語を読ませるテクニックなど光るところが多いのでもったいないと思いました。
◆テーマ部門 金賞『母の思惑』南木野ましろ
【あらすじ】
母の愛を信じられない娘と、母のことを知りたい息子。タイムリミットは、四十九日。
幼少期に生みの母から虐待を受けていた睦月は、父の再婚により新しく母となった養母のことが誰よりも大好きだった。父亡き後も母と二人で穏やかに暮らしていたが、そんな日々は突如終わりを告げる。母に病気が見つかったのだ。
残された時間はあと僅か。そんな中、睦月は母から一通の手紙を投函するよう託される。宛先は母の姉。その手紙以外、睦月には何のメッセージも残さないまま、大好きな母はこの世を去った。
彼女の死後、睦月のもとに冴木という一人の男が訪ねてきた。彼は自分のことを、睦月の養母の実子であると言う。しかも、あの日睦月が投函した手紙は、母の姉ではなく冴木に宛てたものだったらしい。実子の存在を知らなかっただけでなく、自分ではなく冴木にだけ手紙を残したという事実に、睦月は大きなショックを受ける。さらに冴木は、自分の知らない母のことを教えてほしいと言い出し……。
【鈴木 征浩】
女性を主人公に、男性との出会いと恋を描くという王道展開は、決して悪いものではありません。王道には王道たる理由があります。しかしながら、王道は王道であるが故に、マンネリを生みやすく、埋もれてしまいやすいということもまた事実です。
王道の型や枠ありきで、登場人物やそれらの行動などを、その枠のようなものに当てはめるように執筆されているのかな、という印象を受けました。もしそのようなスタイルで臨むのであれば、王道としての道の掘り下げを追求しないと埋もれてしまい、思いが読者に届きにくいと思いますので、王道作品としての深さやオリジナリティの追求を強く意識していただくとより良くなるのでは、と感じました。
王道作品というものは、意外性が少ない代わりに読者に安心感を与えてくれるというプラス面があるものですが、そこで終わらず、その中で作品の、そして著者の色を、追求していただければ、と思います。
【宮川 和夫】
登場人物のキャラクター設定も内容もライトノベル感があり、最後までテンポよく読めました。主人公の睦月も恋に落ちる相手の冴木の姿や表情もよく描けていますし、クライマックスからエンディングに向かう描写も好きです。
ただ気になるところは、冒頭の冴木の言葉づかいの豹変と舞台が関西なのに皆標準語というところです。
大賞まであと一歩という理由の一つは、この内容が果たしてハナショウブ小説賞の大賞を授賞する作品として必要十分条件を満たしているかということだと思います。
◆テーマ部門 銀賞『二通の手紙』のがみなみ
【あらすじ】
消えてしまった父と残された家族を結ぶ、二通の手紙に隠された真実とは――。
律香の父は頼もしい人であった。それと同時に、仕事一辺倒な人でもあった。災害が起こると、父は家族を置いて職場に駆けつける。それは、阪神淡路大震災が起こったあの日も同じで、律香と母は「無事で帰ってきて」と父を送り出した。父の職場の近くには、姉の住む下宿先がある。姉の様子も見てきてほしいと頼んだが、姉は地震が原因で亡くなり、あの日以降、父は帰ってこなかった。
父が行方不明のまま時が過ぎ、律香は父の記憶を心の奥底にしまいこんでいた。ある日、育児サポートを依頼している雲丹亀の自宅で一枚の写真を目にする。そこには、あの日見送った父の姿があった。雲丹亀は、写真に写る男性が律香の父であることを知ると、とある包みを取り出す。そこにあったのは、父から律香への手紙と、そして……。
【鈴木 征浩】
阪神・淡路大震災による家族の喪失という非常に重いモチーフを用いた物語で、描かれている被災者の心情は、胸に突きつけられるものを感じました。
半面、各場面が足早に感じられ、密度が薄い、そしていわゆる「ご都合主義」と呼ばれるような展開に過ぎるのでは、と感じる箇所がありました。モチーフが重厚なだけに、ラストを含め、ひとつひとつの要素や展開を、もっと丁寧に描くことができれば、と思いました。
また、震災被災者を、その心情を、リアルに描くために、絶対的に必要な要素であろう関西弁が用いられていなかったことも、残念に感じました。被災という極限の状況においては、被災者の言葉は普段使っている言葉になるはずで、そういった言葉を用いなければ描けないものがあるはずです。小説としての読みやすさを意識されての選択だったかもしれませんが、本作に置いてはそれが強い違和感になってしまっていることが非常に残念でした。
【宮川 和夫】
阪神淡路大震災をテーマに、行方不明になった父親との絆と主人公の再生を描くドラマで、心を揺さぶられました。その中で気になった所を幾つか指摘します。
1.関西が舞台なのに登場人物がみな標準語であること。2.別れた夫が何故河原でブルーシート生活をしているのか。3.夫と別れたきっかけが不自然ではないか。4.夫の友人がゲイである告白は必要だったのか。
最終選考に残る力はあるので、プロットから見直して是非再チャレンジしてほしいと思いました。
◆テーマ部門 opsol book賞『文車』藍田陽彦
【あらすじ】
消えない罪の意識。秘密を共有し、それでも二人は生きていく。
畦倉浩輔と丘史恵は、同じ大学に通う同人仲間だった。卒業後は交流が途絶えていたが、四十年の時を経て、ふとしたことがきっかけで手紙のやりとりが始まる。
あの頃、畦倉は丘に好意を寄せていた。しかし、丘は同じく同人仲間であり畦倉の大親友でもある野口と付き合っていた。親友と恋のライバルとして争いを繰り広げる中、野口が丘にプロポーズをしたことで、畦倉の恋に終止符が打たれた、はずだった。
社会人となり、数年の時が過ぎたある日。フリーライターになった畦倉は、若手銀行マンとして働く野口へ取材をすることになった。取材後、畦倉が野口の誘いでとある場所に向かうと、そこで悲惨な事故が起こってしまう。
長年秘め続けてきた想いと、忘れることのできない“あの日”のこと。二人が交わす往復書簡により、止まってしまった時計の針が動き出す――。
【鈴木 征浩】
小説文としての文章力が非常に高く、そういった観点では、最初から最後まで非常にスムーズに読むことができました。
惜しむらくは、物語の流れとしての魅力を描き切れていないと感じるところです。それぞれの要素・エピソードについて、物語の中での必然性を感じにくいものや、密度が低く感じるものがあり、それらについてよりブラッシュアップされれば、という思いです。重要登場人物の死に代表されるそれらの要素が、もっと意味を持った、多面的なものとして描かれたなら、と感じずにはいられません。
大部分で往復書簡のスタイルが採られており、「手紙」というテーマ・モチーフがもっとも有効に用いられていた作品であり、文章力も確か。自身の描きたいもの、表現したいこと、そういったものをより明確にイメージし、それらと向き合っていただけたなら、さらに良い作品になるかと思います。
【宮川 和夫】
往復書簡の形を取り、その中に小説を組み入れ、男二人女一人の恋愛模様を描く作品で、恐らく著者の歩んできた歴史も反映しているのかと思います。
文章力、表現力ともに優れていると思いますが、シニア世代の恋愛模様の世界線に入り込むことがどうしてもできませんでした(私の読み手としての力不足です)。
とはいえ、今後オーバー60,70世代の書き手の登場を期待してやみません。
選考委員・宮川 和夫より
全体を通して言いたいことは、皆タイトルの付け方がよくないということです。
タイトルは読者を物語に誘う最初にして最大の武器です。あだ疎かにしてはいけません。小説を書いて終わりではなく、最後の最後までタイトルにこだわってください。
総評
ハナショウブ小説賞も、第3回の最終選考を迎えることができました。
先ずは、大切な作品を、ご応募というかたちで弊社にお預けいただきました著者の皆様に、深く御礼申し上げます。そして、長編作品を書き上げるという偉大な行為に対して、心より敬意を表します。
今回は新たな取り組みとして、エッセイ部門を創設させていただき、医療・介護・福祉にまつわるエッセイを募集させていただきました。
おかげさまで多数のご応募をいただくことができ、様々な方の目を通した様々な医療、介護、そして福祉に触れることができました。応募者の皆様は、年齢、性別、ご職業、お住まいの地域、そういったものは実に多様であり、もちろん表現されている内容も千差万別なのですが、半面で、医療、介護、福祉というものについて、共通した何かを感じもしました。そして同時に、そういったことをエッセイという形にするということの意義も、再確認させていただくことができました。
結果的に10名の方に授賞させていただくことになりましたが、残念ながら受賞とはならなかったたくさんの作品それぞれに、文章に込められた何かを感じたということ、謹んで申し添えます。ご応募くださった皆様、本当にありがとうございました。
そして今回は、第3回にして初の、opsol部門ならびにテーマ部門の大賞受賞作該当無し、という結果となりました。
この結果に至るに当たり、選考委員会では熱い議論が交わされました。大賞を授賞し作品を世に送り出したい、そんな強い希望を持って選考に当たっている選考委員たちは、同時に、過去の大賞受賞作と正々堂々と肩を並べていただける作品でなければ授賞させていただくことはできない、という、使命感と覚悟とを持ち合わせています。そんな選考委員会の苦渋の決断でありますことを、選考委員長として謹んで表明いたします。
その上で、応募作品の全体を通じて感じたことをいくつかご紹介させていただきます。
まず、タイトルについて、非常に残念に感じる作品が多く見受けられました。タイトルはまさに、作品を象徴するものであり、作品を背負って立つものです。それ故にタイトル付けという行為は大変な苦難を伴うことが多いものですが、それでも、相応しいタイトルを付けるということは、その作品に最後の命を吹き込む行為であり、避けて通れないことだと考えています。自身の作品ととことん向き合い作品を象徴するタイトルを付けるということに、もっともっとこだわっていただきたい、と強く思います。
そして、書き終えた後、全体を通じた通読・見直しを、丁寧に行っていただきたい、ということもまた、強く思いました。執筆は本当に大変な行為で、小説を書くという行為はある種生命を削る行為だと思っています。それ故に、書き続けること、書き終えること自体が難しいあまり、書き終えた後の通読が飛ばし読み気味になってしまったり、見直しをする気力が沸きにくくくなってしまったりする方も多いだろうと想像しています。しかしながら、作品がさらなる高みに登るためには、冷静な視点での確認が不可欠です。それをすることで作品の質は確実に向上すると確信していますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
最後に、自身の書きたいこと・表現したいものやテーマと、とことん向き合い、試行錯誤していただければ、と思います。小説というかたちで何かを表現するのは容易ではありません。根幹の部分とどれだけ向き合うことができるか、そしてトライ&エラーを繰り返すことができるかによって、作品の進む道を適正化できる可能性は大きくなると思いますので、ぜひ、と思います。
改めまして、今回もたくさんの情熱溢れる応募作品と向き合わせていただくことができたこと、心より光栄に思います。皆様、本当にありがとうございました。
ハナショウブ小説賞は第4回も開催予定です。ぜひまたそちらに挑戦していただけましたら、と願っております。
2025年3月31日
opsol株式会社 代表取締役社長
opsol book代表 鈴木 征浩
三重県伊勢市小俣町の出版社
オプソルブック
opsol book
(opsol株式会社 opsol book事業本部)
〒519-0503
三重県伊勢市小俣町元町623番1
TEL:0596-28-3906
FAX:0596-28-7766