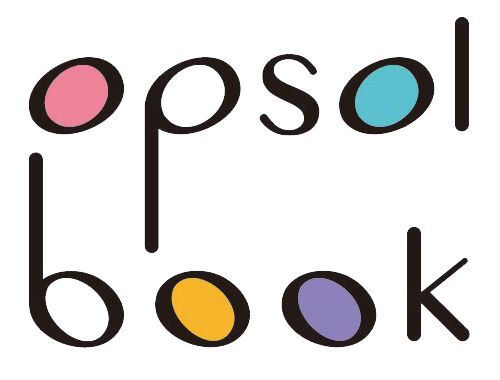第3回ハナショウブ小説賞 エッセイ部門 入選作品
第3回ハナショウブ小説賞 エッセイ部門 入選作品
『医師が深刻な症状で病院にかかって気づいたこと』吉村史年
『悲しい背中』おは
『グリーンのアイシャドウ』石川莉緒
『車椅子のカラヤン』野間栄子
『桜道』高鳥珠代
『障がい者の就労支援』北乃宙
『新人カラスの発声練習』秋田柴子
『食べてただいま』大島絆
『小さなヒマワリの思い出』空滝大地
『我が家の灯』杉本あずさ
『医師が深刻な症状で病院にかかって気づいたこと』吉村史年
それは、休日にオンラインのシューティングゲームをしている時に起こった。私は、中毒性のあるそのゲームで負け込んで、夕方になっても部屋の電気も点けず、苛立ちながらひたすら見えた敵を撃っていた。
右側から不意に敵が現れる事が多くなった。疲れて集中力が落ちているのだと思った私は、鮮やかな逆転勝利を収めたところで、ゲームを終え、部屋の電気を点けた。
右眼に違和感があった。右下の部分が真っ暗で見えないのだ。最初は明るさに慣れるための明順応に時間がかかっているのだと思った。しかし、五分、十分と経っても、右眼の右下四分の一はずっと見えないままで段々と焦りを感じ始めた。これは目の疾患による視野狭窄ではないかと思い至ったからだ。
努めて冷静になろうとした。しかし、夕方遅くまで診療している眼科を探すためにスマホを操作する指は震えていた。内科医師である私は、学生時代の記憶から視野狭窄を起こす疾患が何かを考えた。すぐに浮かんだのは緑内障と網膜剥離だ。他にもあるだろうが、頻度の高い疾患はこの二つだった。特に後者は強度近視を持つ私がいつかはかかると覚悟していた疾患だ。どちらもすぐに治療を受けないと失明に繋がる。
まずい、私は夜遅くまで受付をしてくれる眼科クリニックがある事を突き止め、取るものも取りあえず家を出た。
駅までの道のり、ずっと失明の恐怖に怯えていた。これまで眼鏡で矯正すれば見えるのが当たり前だった世界が失われる。何度も気のせいだ、思い過ごしだと自分に言い聞かせながら歩いた。途中で何度も右眼で遠くを見てみたが、やはり右下が暗くて見えていない。気のせいじゃない。不安になる自分に、今はできるだけ視力を守る努力をすべきだと言い聞かせ、駅へと急いだ。
電車の中では、紙とペンを取りだして、自分の症状を記載した。自分が外来診療をしている時、患者さんが時系列に沿って話をしてくれると、とてもわかりやすくて診断に集中できていた事を思い出し、何時何分に何が生じたか、その後どう変化したかを箇条書きで読みやすいように記載した。そして、薬のアレルギー歴や既往歴がない事も書き加えているうちにクリニックの最寄り駅に到着した。
受付終了間際に駆け込んだ眼科で、受付の女性は、私の問診表と電車で書いたメモ書きを持って、視覚技能士らしきスタッフに相談に行った。そして、そのスタッフは渋い顔をして言った。
「今日は遅く、しかも検査日ではないので詳しい検査はできません。来週の検査日に来て下さい」
ここで思い起こしたのは、学生時代の知識だった。来週の検査日まで五日もある。もし、予想している疾患だったら、この五日間で手遅れになりかねない。私は彼女らに頭を下げた。
「医師に繋いでください。眼圧検査と眼底検査だけでいいのでお願いします。それで異常が無ければ帰りますので」
すると、スタッフは眼科医に取り次いで、すぐに検査を始めてくれた。眼底写真を撮り終えて数分もしないうちに、私は診察室に呼び出されていた。
「網膜剥離ですね。緊急ですので、手術のできる病院に紹介状を書きます」
眼科医の言葉に、やっぱりという絶望感と、診断がついて良かったという安心感が混じり合った。医師は私の家から比較的近い大きな眼科医院に紹介状を書いてくれた。翌朝一番に、紹介状を持ってそこに行き、すぐに手術の日程を組んでもらった。こうして手術を受けられたお陰で、右眼の視野はほんの少し欠けただけで、失明を免れる事ができた。
今回の経過を振り返ると、気づきが二つ得られたように思う。一つは医師が他の医師を受診する難しさだ。医師というのはなまじ知識があり変にプライドがある。私が他の医師を診察していて感じるのが、高圧的な態度で受診してくる人が多いという事だ。特に年長の医師は、つい自分の専門知識をひけらかして、自分の思い通りに治療させようとしてくる。私は、それが相手に悪感情を持たせる事がわかっていたので、プライドを振りかざさず自分の予想と最低限の要望だけを伝えた。もう一つは、眼科診療の時、終了時間間際でも検査してもらったというありがたみだ。正直に言うと、私も内科診察で受付終了間際の患者さんを診ることは診るが、心の中では「もっと早く来てくれたらいいのに」と愚痴をこぼしていた。しかし、患者さんも好きで夜遅くに病気になるわけではないのだ。仕方がない事もある。それなら、多少帰りが遅くなっても、診察に集中してお互い気分よく帰れるようにしよう、そう思った。
普段診る側が、診られる側に回る。今回の疾患で視野をほんの少し失ったが、得られた学びは小さくない、そう思った。
『悲しい背中』おは
忘れられない光景がある。
もう10年以上前のこと。老人ホームにてボランティアをしていた時期があった。ホーム併設のデイケア利用者の話し相手になったり一緒に体操やレクリエーションを楽しんだり、といった活動内容である。今にして思うと自分のような知識や経験のないオネエチャンがいても特に役に立つことはほとんどなかっただろうが、それでも施設スタッフをはじめ、実に色々な方に良くしていただいた。
初めて身を置く介護の現場。辛い、汚い、苦しい……そんなイメージとはうらはらに、スタッフの皆さんの笑顔は常に絶えることはなく、とても明るい現場であった。
ある日。いつも来るおじいさんの姿が見えない。デイ利用にもきちんとスーツを着てくる反面、冗談が好きなお茶目なおじいさんだった。翌週も来なかった。そのまた翌週も……。おじいさんが肺炎をこじらせ、帰らぬ人となってしまったことを、業務開始前のカンファレンスで聞いた。
いままで元気でいたはずの人が突然、帰らぬ人となる。私には衝撃的なことだった。だって、どんなに会いたくてもおしゃべりしたくても、地球のどこを探しても、もうその人とは出会えないのだ。さすが職員の面々はプロであるがゆえ、悲しさを他の利用者の前では表に出さない。介護の現場ではこういったことがいつ起きてもおかしくはない。いつか慣れたりするのかな……なんて思いがふと胸をよぎってしまった。
その日の夕方、デイケアが終了し、利用者が帰宅してがらんとしたデイルームの椅子に、スタッフKさんがひとり、座っていた。どうされましたか、と声をかけようとして、はっとした。その椅子はいつも、亡くなったおじいさんが座っていたお気に入りの場所だった。太陽のあたる、外の景色がよく見える場所。その席を秋の夕焼けの日差しが照らす。光が優しく包み込んでいるようだった。声をかけようにもかけられず、少し離れたところで、私はただその後ろ姿を見ていた。
と、ぽつんと座るKさんの腕が動いた。優しく机に触れ、自分の座る椅子に触れる。何を慈しんでいるのか分かり、思わず喉がぐっと鳴った。何が慣れだ。少しでもそんなことを考えてしまった自分を恥じる。
悲しくないわけがないのだ。苦しくないわけがないのだ。
いろいろな思いを抱えて、それでも毎日笑顔で利用者に接することがどれほど大変なことか、私は痛感した。
あの時のKさんの切ない後ろ姿を私は今でも忘れることができない。
悲しみと、愛おしさを包むような西日が、とても優しかったことも。
『グリーンのアイシャドウ』石川莉緒
「グリーンのアイシャドウがいいのよ」
さっきまで口も利けないほど気持ちが落ち込んでいたのが嘘のように、祖母はハキハキと要求した。
茶色いアイシャドウを祖母の瞼に塗ろうとしていた私が手を止めると、
「グリーンが一番日本人の肌に合うし透明感も出るんだから」
と明確な理由まで語りだすので、余計面食らう。
久しぶりのメイクに挑む祖母の意志は固いが、祖母のドレッサーには何も入っていない。
祖母が一人暮らししていた家を出ていく際に、私が中身をほとんど破棄してしまっていた。
私は自分が持ってきたコスメポーチの中を慌ててごそごそ探し始めた。
中程度の認知症を患っている祖母は、施設に入所してから目に見えて短期記憶力が低下していった。
自分が言ったことでも五秒もすれば忘れるから、言っていることがコロコロ変わる。食べたいものや行きたいところでもなんでも。
祖母の気分や要求にそぐわないことをすると激昂させてしまい、最終的には食事や会話も儘ならなくなるほどふさぎ込んでしまう。
自分の欲求もわからなくなるほど記憶がもたないのだから、混乱し不安になってしまうのは当然だ。
実際、白髪を染めたいと泣き喚いた翌日に施設に迎えに行くと、「髪の毛を染めたいなんて言っていない!」と吐き捨てふて寝してしまった。
私は鬱のスイッチが入るときに祖母が見せる暗く澱んだ目に泣き叫びそうになることがある。
だから、祖母と接するときは、機嫌がいいときでも神経を使う。
コロコロ変わる要求や気分にいちいち理由を求めてはいけない。
そんな祖母が久々に「日本人の肌に合うから」とわかりやすい理由まで添えて、明確に意思表示をしてくれている。
元々おしゃれが大好きな祖母だから、大慌てで入所した施設にある最低限の荷物では満足にファッションを楽しめなかったのだろう。
認知症になろうと好きなものを丸ごと忘れてしまうわけではない。
寧ろ、限られた記憶力の中でより鮮明で大切な存在になっているに違いない。
「おばあちゃん、グリーンのアイシャドウあったよ」
私はうやうやしくアイシャドウを差し出した。
茶色やピンクなど暖色のアイシャドウが主流の中で、グリーンはやや突飛な色だ。
たまたま私のポーチに入っていたのは今でも奇跡だと思う。
祖母は、きらきら光るうぐいす色のアイシャドウをじっくりと確認すると、「これ塗って」と瞼を閉じた。
偶然見つかったグリーンのアイシャドウだが、正直気に入ってもらえるか不安だった。
見た目がグリーンなのは確かだが、実際に瞼に塗ると殆ど発色しないのがわかっていたからだ。
僅かにちらちらと緑色に光る繊細なアイシャドウを今の祖母にわかってもらえるか。
なるべく濃く塗りたくて何度もブラシをガシガシと往復させた。
「あら、いいじゃない」
恐る恐る祖母の顔を覗き込んだ私に祖母は合格を出した。
そのあとも祖母のメイクを見守っていると、祖母は瞼に限らず、同じところを何度も塗っているのがわかった。
眉毛がどんどん濃くなっていく。
眉毛が済むとリップをぐりぐり塗り、また極太になった眉毛に戻る。
充分濃くついている化粧品を認識できず、「ねえ、ちゃんとメイクできてる?」と鏡ではなく、私に何度も確認する。
そのたびに「すっごくきれい!」と私は心からの賛辞を贈った。
施設に入所してから、祖母の笑顔をあまり見なくなった。
優しい施設スタッフや友達になってくれる入居者にまで恵まれてこれ以上の環境は求められないのに、祖母はどんどん消耗していく。
まだ自分は年寄ではないのになぜデイサービスに行かないといけないのか。
自分はデイサービスに行きたくないといっているのに、甘いお菓子で釣って無理やり参加させようとしてきて腹が立つ。
ずっと一人暮らしをしてきた祖母が簡単に集団生活に慣れるわけはないと覚悟していたつもりだったが、抗うつ剤に頼らないとまともに日常生活も送れなくなった祖母を見て、いっそ仕事を辞めて在宅介護をした方が幸せなのではないかと何度も考えた。
自分は認知症なんかじゃない、まだメイクもできる、施設に帰ったら他の年寄よりも目立ってやらなきゃ!
ドレッサーに向かう祖母のメイクは、ただのおしゃれではなく、自尊心をかけた必死の戦いだった。
その自尊心が揺らぐたびに、「メイク、すごくきれいだよ!」と私は激励した。
メイクが仕上がると、祖母は極上の笑顔でヘアスプレーの代わりにドライシャンプーを何度も髪の毛にかけていた。
認知症は一度患うと、一気にすべてを忘れ、何もかもを認知できなくなるわけではない。
段階によっては、まだまだ残っている認知力によって不安も喜びも倍になる状態だと思う。
その認知力から見える世界で生きていくには、いつだってほんの少しの嘘と絶対的な自己肯定感が必要だ。
その日、私は祖母に全身コーディネートしてもらっている。
子供服に身を包んだアラサーの私も、初めて自分を肯定できるような気がした。
『車椅子のカラヤン』野間栄子
障がい者施設での実習四日目。私は宇都宮さんの部屋に行った。ノックをすると、車椅子に乗った初老の男性が現れた。
「職員の○○から聞いてるよ」宇都宮さんはくすくす笑いながら言った。「あの職員がさ、実習生に色々教えてやれって。今日はよろしくね」
「よ、よろしくお願いします」
部屋の壁には指揮者のポスターが貼ってあった。
「僕はカラヤンが好きでね」
宇都宮さんは「ついてきて」と言いながら、電動車椅子を器用に動かして私を施設の一角に誘った。車椅子が置いてある。
「今日は1日車椅子で過ごしてもらいます。あなたは若いから手動のやつ使おうか。僕は老人だから電動を使わせてもらうけど」
「……」
私は車椅子に乗った。視界が一気に下がる。
「さあ、障がい者の世界へようこそ」
施設を出ると、すぐに汗ダラダラになった。道がでこぼこしている。手動の車椅子を漕ぐのがこんなに大変だとは思わなかった。私は明日の筋肉痛を覚悟した。
「本でも買うか」
宇都宮さんはそう言いながら本屋に向かった。すぐに、中から店員さん達が出てきた。
「いらっしゃいませ! 段差がございますので、お手伝いいたします」
店員さん達はにっこり笑って車椅子を持ち上げてくれた。ついでに私の分も持ち上げてくれた。
「お手の届かないところに本がありましたらお声がけください」
「ありがとう」
店内がとても狭く感じる。平積みの本を落としてしまいそうになった。宇都宮さんは『カラヤン、クラシック音楽の帝王』という本を購入した。
「ね、段差があってもバリアのない所は過ごしやすいでしょう?」
確かにそうだ。入り口の階段はバリアフリーじゃないけれど、あの本屋さんは非常に過ごしやすかった。
「ここからちょっと嫌な思いをしてもらいます。障がい者をめちゃくちゃ嫌うファミレスに行きます」
「え?」
「あなたは社会福祉士になるんでしょう? 僕たちを助ける立場になるわけだよね」宇都宮さんはすごく真面目な声で私に言った。「野間さんね、僕は絶対にあなたに経験しておいて欲しいんだ」
私は緊張してファミレスに乗り込んだ。なんの変哲もない町のファミレスだ。
「いらっしゃいませ……あのう、お付き添いの方は?」
「私たち二人ですが」
「申し訳ございません」張り付いた笑みを浮かべたウェイトレスが言う。「お付き添いのない障がい者の方は入店をお断りしているんですよ」
「そうですか」そう言って宇都宮さんはカラヤンが指揮するように目を閉じた。
「ですから……」
「お茶を一杯だけ飲みたいんですがね」宇都宮さんはカラヤンのように堂々と言った。「僕は介助なしでお茶も飲めるし、トイレにも行ける。お金だって持っています」
「でも、お連れ様は……」
「野間さん? あなた一人でトイレ行ける?」
「はい!」
私は答えた。
「彼女、行けますよ。ダメですか?」
「……」
私たちは入店を許された。宇都宮さんはアイスコーヒーを注文した。疲れたでしょう? 甘いものでも頼んで下さい……。宇都宮さんがそう言ったので、私はメロンソーダを注文した。宇都宮さんが言った。
「僕はここへ来る度に自分の胸に黄色の星がついている気分になる」
「……」
「悪いのはあのウェイトレスさんじゃない。付き添いのない障がい者を入れないって決めた上の人だ」
やがて先ほどのウェイトレスさんがアイスコーヒーとメロンソーダを持ってやってきた。
「先ほどは……あの……大変失礼を……」
「あなたは悪くないですよ。そうでしょう?」
「……」
彼女は私達に丁重に頭を下げた。彼女の後ろ姿は泣いているかのように震えていた。
「一人ひとりはいい人なの。でも、上に立つ人が間違ったらいい人も悪い人になるの。それだけなんだよ、野間さん」
ポツリと宇都宮さんはそう言って、悲しそうに笑った。
『桜道』高鳥珠代
『満開の桜を見に散歩に行こう!』
それが募集の内容だった。定員が五十人の施設の中で、たった四人の参加者。このポスターを見たほとんどの入所者は、そんなの自分で行けるからいいよ、と思ったに違いない。
ここは自立型老人施設、基本的に自分のことは自分で出来る人の集まりである。だから散歩なんて連れて行ってもらわなくても自分で行ける。それでも参加を希望した人たちは、普段から積極的に出掛けられない出不精な人や、杖を使いながらならゆっくり歩けるのだけどといった人だった。
散歩といっても、施設から近くの公園までは車で向かう。ワゴン車の大きなシートに、皆頼り無げにちょこんと座る。コロナは一応収束したとはいえ、マスクなし、狭い空間でのおしゃべりはご法度である。それぞれが黙って窓の外を眺める。ようやく始まったイベント、みな表情が硬い。外に出るという不安な気持ちを表すように、シートベルトで固定したはずの身体が、荒い舗装の道をガタガタ走る車と一緒に、ガタガタと不安定に揺れる。
着いたのは、施設から車で五分ほど離れた場所にある、大きなグランドをいくつか備えた総合公園だった。グランドをぐるりと囲むように敷かれたアスファルトの道に沿って、桜が植えられている。その桜の帯のような道を、皆でゆっくりと歩く。耳が遠いうえ杖を使わなければ歩けない女性と、認知症がだいぶ進みだした女性のふたりが、段々と集団から遅れ始め、いつしか集団はふたつに別れた。私は遅れ始めたふたりに歩調を合わせる。前の集団の背中が段々小さくなっていく。
「もう仕事には慣れましたか?」
ひとりが、覗き込むように私に問いかける。
「いえ、まだまだです。皆さんのお顔と名前が一致しなくて……。新しい仕事も全然覚えられないし」
答えながら涙が出そうになった。定年退職と同時にした転職。同じ事務職とはいえ、一般企業から、まったく勝手が分からない介護施設に飛び込んだ。『そんなにいい職場、よく見つかったね』とまわりからは羨ましがられた。『たまたまね、運がよかったわ』と答えるその時の私は、自信と希望に満ち溢れていた。満ち溢れていた転職だったはずなのに……。風に散る桜の花びらを目で追いながら悲しくなった。事務職と言っても、イベントやお出掛けの付き添いや総務や会計など、入所者に関わることは山ほどある。人と関わることは好きだったのに、慣れない仕事は何をやっても失敗ばかりだった。
「大丈夫ですよ。なんでも無理しないで、ぼちぼちですよ」
その不安な気持ちを推し量るように、ひとりが優しい眼差しで私を見つめる。
「ほら見て、桜のトンネルみたいね。桜道を通るときは、新しいことが始まるってことなのよ。だから焦っちゃ駄目」
もうひとりが振り返り、耳が遠いからか大声で話す。その言葉を聞きながら、私は小学校の入学式を思い出していた。あのときも、街角で迷子になったときのように、不安な気持ちで一杯だった。入学式の会場となった、幼稚園のホールとは比べものにならない位大きな小学校の体育館に、その日初めて会った子と手をつないで入場する足どりは、前の日までのとは違って、背中のランドセルのように重かった。あの日は、きょうと同じように体育館までの道に桜の花びらが舞っていた。
みなを喜ばせるために来たはずの散歩で、逆に私はみなに励まされていた。淡桃色の桜の花びらが、フワリと吹いてきた風にあおられて、ヒラヒラと舞う。花冷えの中、定年と同時にまた一年生になった私の心は、ここに着いたより温かかった。焦らずに、こんな風に少しずつ関わりをもっていけばいいのだと気づかされた。永く生きている人たちはやっぱり凄い、敵わないなと思った。駐車場の隅に見え始めたワゴン車に向かう私の足取りは、降りたときよりも軽くなっていた。
『障がい者の就労支援』北乃宙
「内定もらったよ」
3年前のこと。いつもはもの静かなAさんが飛びっきりの元気な声で窓口に駆け込んで来た。見た目はごく普通の18歳の好青年であるが、実は統合失調症を抱え、知らない人と話もできず、引きこもりがちだった。
私は現在、湘南の福祉事務所で主に生活保護受給者の就労支援をしている。ずっと民間会社でモノづくりに注力して来たが、定年後は地域社会に少しでも役立つ仕事がしたいと思い、就労支援に舵を切った。
私がAさんと出会ったのが、8カ月前だった。初めて面談した時はヒヤリングも思うように進まず当惑したことを覚えている。
「得意なものを教えて」
「どんな仕事をやりたいのかな」
やさしく尋ねたつもりだったが、口を閉ざしたまま。これでは就労支援以前の問題だ。どうしたら心を通わせることができるか。
そこで私が取った方法はポンチ絵だ。かつて若かりし頃、開発会議の場で、仲間とアイディアを白板に書きなぐったことがあった。その経験を思い出した。
働く意義や喜び、社会との交わり、さらには将来の人生設計まで、就労に関連したキーワードをおもいつくままに語りかけながら書き、それを〇で囲む。次に、それらの課題や解決策のキーワードを自分に言い聞かせるように記入し、同様に〇で囲み、これらを線で結ぶ。これが私流のポンチ絵だ。こうして話しながら絵図にし、最後に面談者に渡すことで、情報が残り安心感を与えることになる。
「面白いね」
Aさんがポンチ絵を手にした時、笑みがこぼれたのを私は見逃さなかった。
昨今、コロナが落ち着いたとは言え、雇用環境は依然として厳しい状況が続いている。とりわけ事務職は高い競争率が待っている。障がい者の場合も例外ではない。障がい者手帳を持っていれば、障がい者雇用枠の求人もあるので表面的には難しくなさそうに思えるが、そもそも障がい者雇用枠の求人は圧倒的に少なく、また就業場所や業務も限定されるため、希望する仕事に就くのは容易ではない。
Aさんの場合、就労移行支援事業所の利用経験もあったが、なかなか就労には至らなかった。回り道をしながら、福祉事務所へ相談に来られ、私の出番となった。生活保護受給者の中にはさまざまなハンディを抱えた人がいる。幼子を抱えた母親、身体疾病者、出所者、そして障がい者。就労支援で欠かせないのが就労意識である。これが備わっていないと、どんなにいい求人を探しても、応募手助けをしても、功を奏さない。
就労支援の面談は通常、月1回のペースで行っている。私はAさんに対して、面談の都度、このポンチ絵方式を繰り返した。毎回、キーワードは微妙に異なるが、それがかえってAさんにはいい刺激になったようだ。5カ月が過ぎ、明らかに変化が起きた。Aさんが自分から発言するようになったのだ。
こうなればしめたもの。意思疎通ができ、就労意識が高まればきちんと就労支援に進めることができる。Aさんに適した障がい者求人を懸命に集め、その仕事の厳しさ、得るもの、将来の可能性などをアドバイスし、応募するかどうかの見極めを行った。一旦、応募を決めたら、今度はそれに受かるための作戦を練る。最も大事なことは、応募職でどう取り組むか、を自分の言葉で仕上げることだ。
「経験がないからわからないよ」
Aさんが反発したことがあった。
「確かにどの仕事も初挑戦だから、難しいよね。だったら、どう仕事に向き合うか、素直な気持ちを書けばいい。どうしても浮かんで来なかったら、学びたいことでもいい。自分でポンチ絵を作ってごらん」
私の激励に大きく頷いた。面接リハーサルもした。元来、話すのが苦手なAさん。それでも私との信頼関係ができてからは必死に食らいついて来た。でも、Aさんは就職面接で2回落ちた。確か3回目の応募だったと思う。Aさんは見事、念願の事務職就職という吉報を手にしたのだ。今まで見せたことのない笑顔に、私も心が躍った。
就労支援は福祉の分野では裏方の地味な存在かも知れないが、私は誇りを持っている。並大抵の苦労ではないが、うまく行けば障がい者を含め、多くの社会的弱者とあふれんばかりの喜びを分かち合うことができる。これ以上、幸せなことがあろうか。
『新人カラスの発声練習』秋田柴子
以前、街の小さなクリニックに勤めていたことがある。
広い意味では医療もサービス業に含まれるが、普通のそれに較べるとかなり趣が違う。何しろ病院で提供されるのは、およそ人には好まれないサービスだからだ。腕に太い針を刺されて血を抜かれる。己の排泄物の提出を迫られる。身体の痛い部分を触られる。誰が好き好んでそんな“サービス”を受けたがるだろうか。
そのせいか待合室で順番を待つ患者さんの表情は固い。少なくともカフェでお洒落な飲み物の出来上がりを待ちわびる時の顔ではない。慣れない頃は次の患者さんを呼ぼうと廊下に出た途端、その強張った顔が一斉にこちらを向く迫力にいささか怯んだものだ。
それゆえ医療者は笑顔必須なのだが、同僚の男性はよくぼやいていた。「こっちは笑顔のつもりでも、男ってだけで怖がられることもあるからなあ」性別でのカテゴライズの難しい昨今だが、彼の言うことは一理あるだろう。
では女性ならばいいのか。否、女性でも威圧感の強い人は存在する。何を隠そう、私自身がその例だ。顔や体型などの外見ではない。問題なのは声である。
私の声は低く固い。ハスキーボイスなどと格好のいいものではなく、文字どおりドスのきいた声の持ち主なのだ。同じ自分の声でも、己で聞くのと他人様が聞くのとでは全く違う。若い頃にビデオで初めて自分の音声を聞いた時は、衝撃で耳を塞ぎたくなったほどだ。以来、話し方に気をつけてはいるものの、勤務当初はずいぶん悩んだ。ここは病院である。心身の不調でナーバスになった患者さんを怖がらせてはいけない。
そこで私は考えた。実はひとつだけ有利な点がある。私はかつて物真似が得意な子供だった。アニメのヤンキーキャラからクラスのぶりっ子同級生、果ては電話の自動音声案内まで、見事そっくりに再現できたのである。甲高いぶりっ子声が出せるなら、このドス声を変えることも理屈上は可能なはずだ。
だが女性の高音は、高齢者の最も聞き取りにくい音と言われている。病院という場所は、小児科などの例外を除けば年配の患者さんが非常に多い。むかし読んだ物の本にも「女性の深いアルトがいちばん聞き取りやすい」と書いてあった。深いアルト! これなら私のドス声でも何とかなるのではないか。それが実現できれば、むしろ好都合のはずだ。
「○○さん、○○××さーん。お待たせしました、どうぞ」
勤務先の規則に従ってフルネームで名前を呼ぶ。もちろん笑顔付きだ。第一印象の良し悪しは、その後の治療にも大きく影響する。それこそ歌手が発声練習をするかのような意気込みで毎日患者さんの名前を呼び続け、やがて半年も経った頃だろうか。
「先生、綺麗な声しとるねえ」
呼ばれた当人とは別の老婦人が、待合室の椅子からこちらを見上げて言うではないか。思わず心臓がどわんと跳ね上がる。
「いえいえ、昔からドスのきいた声って言われるんですよー」
慌てて謙遜してみせるが、老婦人はきっぱりと首を振った。
「そんなことないで、綺麗な声しとるわ。なあ」
「ほんとや。色っぽくて女優さんみたいな声やわ」
絶妙な合いの手とともに、他の患者さんたちが温かい笑顔と頷きを返してくれる。
女優さんの声! 思わず心の中で上げた雄叫びをお許しいただきたい。カラスがウグイスに化け得るなど、一体誰が予想しただろうか。
それから私は、頻繁に患者さんから声を褒められるようになった。
「あれ、今日はあの声の綺麗な先生、お休み?」
だが残念なことに、我が親愛なる同僚はその肩書を聞いても、誰一人として私のことだと思い至らなかった。なぜなら私の“女優声”は、あくまで呼び出しの時限定だったからだ。ウルトラマンの戦闘時間は三分間だったが、私の技が持続するのは患者さんの名前を呼ぶ数秒間のみである。三分間戦えるなら立派なものだ。
とは言え、患者さんを呼び入れた後でもやはり声色には気を遣うし、丁寧な口調も崩さない。それでも時折「先生、話し始めると感じが違うねえ」と呟かれることもあった。
だが医療行為は真剣勝負だ。女性だからと舐められたり過度に甘えられると、洒落にならない支障が生じる。しかも私はリハビリ科勤務だったので、「いいですよ! はい、もう一回!」と患者さんの気分を上げる勢いが必要な時もあるのだ。
しかし何やら患者さんを騙しているようで後味が悪い。せっかくのウグイスがサギになっては困る。そこで私は声を褒められたら自ら宣言することにした。
「あ、この声、三分も持ちませんから。すぐ化けの皮剥がれちゃって、もうウルトラマン以下!」
狭い待合室に控えめな笑い声が起こる。これはこれでいい。病院での笑いは大事な安定剤だ。
そしていつの間にか私の肩書が「声の綺麗な先生」から「お笑い芸人みたいな先生」に変わっていったことは言うまでもない。
『食べてただいま』大島絆
明日の高校生のお弁当用に、きゅうりを刻んでいる。まるまる1本を細切りにして、ビニール袋に入れて塩で揉む。10分ほど置いたら、水気を切り、だしとごま油で味をつける。
緑の彩りを入れたいときに重宝する。きゅうりが苦手という子はほとんどいないし、濃いめの味つけなので弁当にはうってつけ。児童養護施設で働き始めて今年で8年目、ずっと作り続けてきたレシピだ。
他の施設では、日々の食事を調理師に任せるところも多いと聞くが、私の働くこの施設では、生活を見る職員が調理も担う、「全調理」のシステムを大事にしている。就職するまで実家暮らしで、ほぼ料理をしたことのなかった私は、はじめの頃、かなり苦労した。調理だけに集中できるならまだ良いのだが、現場には子どもたちがいるので、彼らを見ながら、キッチンでの作業を同時並行で進めなければならない。揚げ物をしようと火を付けた瞬間に、リモコンの取り合いで喧嘩が始まる。生肉を扱っている最中に、「はさみ出してー」と子どもが頼んでくる。そのたびにこちらの作業は中断、何事も自分のペースを守りたい私にとっては、かなりのストレスだった。いらいらすればするほど、野菜の切り方も味つけもいいかげんになり、おいしいごはんになってはくれない。
それでも続けていれば慣れてくるもので、まともなものが作れるようになると、だんだん楽しくなってきた。おそらく、一緒にチームを組んできた職員の影響だ。たまたまかもしれないが、私の周りには、「食」で気持ちを表現する人が多かった。
アップルパイが得意で、よくおやつに作る人。「世界一周旅行」をテーマに、ハワイ料理やベトナム料理をどんどん作って、遂にテーブルにおさまりきらなかった人。いつも不機嫌そうなのに、ケーキを作るときはすごくいきいきして、子どもの誕生日やクリスマスには、どかんと巨大なケーキを作る人。
節分祭りの夜、私は現場で留守番をしていたのだが、お祭りに行った職員が、私にと、田楽こんにゃくを買ってきてくれたことがあった。また、最近大変そうだからと、過去に組んでいた職員が、杏仁豆腐をわざわざ届けてくれたこともあった。どちらも私の好物だった。私の好きなものを覚えていてくれたことも、ねぎらいの気持ちを込めて買ってきてくれたことも、すごく、嬉しかった。
食べ物は、食べたら後には残らない。でも、込められた気持ちは消えない。形に残るモノのプレゼントも良いが、すぐに消えてしまう、その後腐れのなさが、「食」の良いところだと思う。
どうせ作るなら、できるだけおいしいものを食べさせてあげたい。喜んでいる笑顔が見たい。そのためなら、一手間を惜しまない。それは、子どもにとって、いつか、心が帰っていく記憶になる。悲しいときや苦しいときに、帰っていける先があることは、命の支えだ。こんな「帰る場所」の作り方もあるのだと、施設の職員のあたたかさに、学んできた。それは私にとって、この8年間の、とても大きな救いでもあった。
私が児童養護施設で働いて身につけた一番のスキルは、そんな「食」への向きあい方だと思っている。
『小さなヒマワリの思い出』空滝大地
老健施設の入口正面に、見覚えのある花があった。
子供の頃に今は亡き祖母の見舞いに訪れて以来、約20年ぶりの同施設への訪問になる。遠方の大学を出て医師となり、地元に戻って早10年以上、まさか非常勤医師として、再び訪れることになる日が来るとは思ってもみなかった。
私の知る限り、ほとんどの老健施設において、入ってすぐの所に生け花が飾ってあり、施設の顔のようになっている。これらの花の鑑賞を密かな楽しみにしているのは、きっと私だけではないだろう。大抵の場合は、業者が管理しており、四季折々の美しい花が楽しめる。職員やボランティアの方々による個人作品の施設もしばしばあり、プロの「完璧」な作品に比べると、大らかな味わいがあるものが多いように感じる。
目の前に活けられていた花は後者で、小さなヒマワリのように見えた。後で調べてみるとミニヒマワリというそうだ。数本のヒマワリが凛として咲き誇っていた。色とりどりの艶やかさや、複雑な構成の美しさというようなものは無いが、無骨で真っ直ぐなたたずまいが、私好みだった。職員の方に花について尋ねると、予想通り施設職員の方の作品とのことだった。
何故ヒマワリの生け花に見覚えがある気がしたのか、なかなか思い出せないでいたが、診察のため、部屋を回るうちに、はたと思い出した。入所していた祖母の友人の田中さん(仮名)の部屋で見ていたのだ……。
田中さんは祖母の隣室だった。祖母より少し年上だったのではないかと思うが、認知機能もしっかりしており、いかにも明治生まれという気丈な女性だった。私のことも可愛がってくれて、祖母の見舞いに行った際に部屋に招いていただき、よくお菓子などをいただいた。ヒマワリの生け花は、夏休みに訪れた田中さんの部屋に飾られていたのだ。大好きな花で、自宅で育てていたのだと聞いた記憶がある。
どうして、そんなにヒマワリの生け花が、私の印象に残っていたのかを振り返ってみると、私の中で、田中さんのイメージが小さなヒマワリと綺麗に重なっていたからだと思う。私の祖母にしろ、田中さんにしろ、年齢を重ね腰は曲がってきていても、気骨があるというべきか、心の芯が真っ直ぐに通っている人だった。きっと、子供心に私がヒマワリを好きになった理由でもあるのだと思う。
記憶を取り戻して少しすっきりし、2階のデイルームで、入所者の方と雑談を交わしている内に、ふと窓の外でヒマワリが風に揺れているのが目に入った。見下ろすと、施設の裏庭にかなりの本数の小さなヒマワリが咲いていた。
仕事を終えた後、施設の方に頼んで裏庭を見せていただいた。ありがたいことに、ちょうど普段から花の世話をしているという職員の方がおり、ヒマワリについて尋ねてみた。その職員の方によれば、最近入職したものであまり昔のことは分からないが、元々は入所者の方からもらった種を栽培したものだと前任者から聞いているとのことだった。田中さんのヒマワリかは分からないが、少なくとも私にとっては祖母と田中さんの思い出が確かにそこにあった。
今でも小さなヒマワリを見ると、初心を思い出し、少し背筋が伸びるのを感じる。
『我が家の灯』杉本あずさ
我が家には夕方に、空気が華やぐ時間帯がある。ヘルパーさんが来てくれるのだ。それを楽しみに、仕事から帰ってきて、夕食の準備に勤しむ。子どもたちの様子を見ながら、やることはいくらでもあるし、一日の疲れも出やすい時ではある。それでも、もう少しでヘルパーさんが助けてくれると思うと、前向きに頑張れるので、有難い限りである。
ヘルパーさんは、長男のために来てくれる。長男には、知的障がいやこだわりがある。九歳になるけれども、食事は見守りの上で、時には介助が必要だ。入浴も一人ではできない。それでも一般的には、子育ての範疇として、なかなかヘルパーさんの派遣は認められないようだ。しかし、我が家には他にも事情があって、自治体が福祉に積極的であることもあり、ヘルパーさんが来てくれるのだ。
我が家の事情というのは、まずは次男のことだ。次男には知的障がいは無いものの、こだわりが強かったり過敏だったりするため、大変に手がかかる。次男を抱っこ紐であやしながら、長男の食事や入浴を見ていたときは、なかなかに苦労した。今は更に、三歳になって抱っこ紐に入れておける年齢でもなくなった。次男は夜中によく起きる子でもあり、私はすっかり睡眠不足が慢性化している。そのせいで、頭がよく回らないし、だから家事や育児をてきぱきとこなせない。そう思っていたら、産後うつの診断までもらってしまった。更には、離婚してシングルマザーにもなってしまった。幸いに実家が近く、助けてくれる母はいる。しかし母も高齢で、頼るにも体力の限度がある。そんな我が家に、長男の介護という形でヘルパーさんたちが来てくれることになったのだ。
数人のヘルパーさんが日替わりで来てくれるのだけれど、偶然にも皆さん若い男性で、歳の離れたお兄さん的な存在だ。人見知りの強い次男も、自宅でしょっちゅう会うことで、すっかり懐いた。家に人が来てくれて、お喋りの好きな長男とヘルパーさんの会話が弾み、家が賑やかになった。ヘルパーさんは私の話し相手に来てくれているわけではないし、次男の面倒を見てもらうわけにもいかない。それでも、狭い我が家だし、ヘルパーさんも、長男と次男や私を大きく区別することもなく接してくれる。ちょっとした会話に癒されるし、次男も楽しそうにしていて私のやることが捗る。
長男の人生は、これからも人に助けてもらうことを必要とするだろう。でも、助けてくれる人たちのおかげで、楽しく生きていけるのではないだろうか。更には、私や次男も、長男の家族として、その恩恵にあずかっていけるのかもしれない。
我が家の夕方に訪れてくれるヘルパーさん達は、私たち家族にとって灯のような存在だ。まだ若い彼らの人生もどうか、幸多きものであって欲しい。
三重県伊勢市小俣町の出版社
オプソルブック
opsol book
(opsol株式会社 opsol book事業本部)
〒519-0503
三重県伊勢市小俣町元町623番1
TEL:0596-28-3906
FAX:0596-28-7766