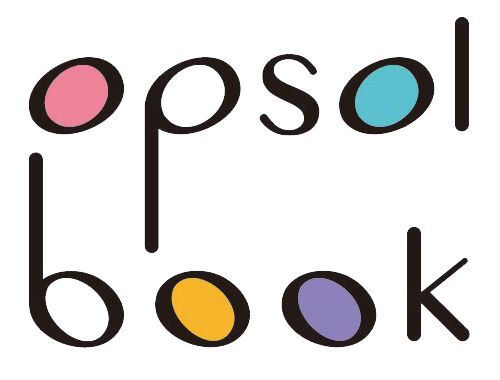【第2回ハナショウブ小説賞】最終結果発表!
第2回ハナショウブ小説賞 受賞作品
このたびは、第2回ハナショウブ小説賞にご応募いただきありがとうございました。
受賞作は下記のとおり決定いたしました。
opsol部門
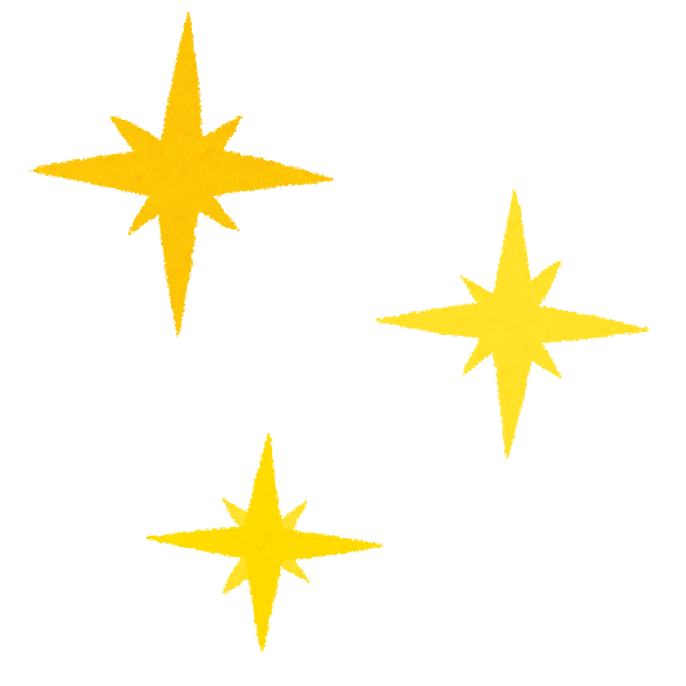 【大賞】賞金30万円+書籍化
【大賞】賞金30万円+書籍化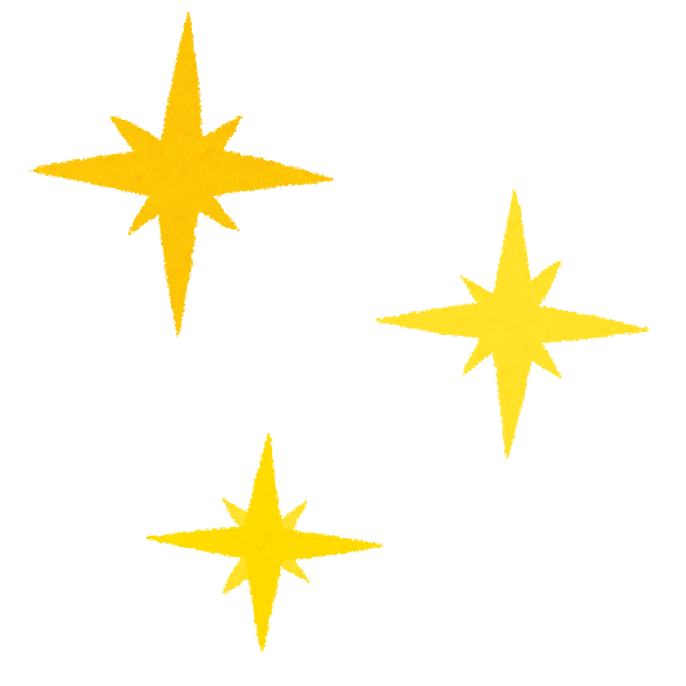
『走れ!スーパー茜号』 小川マコト(応募時ペンネーム:macoty)
*掲載当時からペンネームが変更されたことに伴い修正しています。
【金賞】
該当作品なし
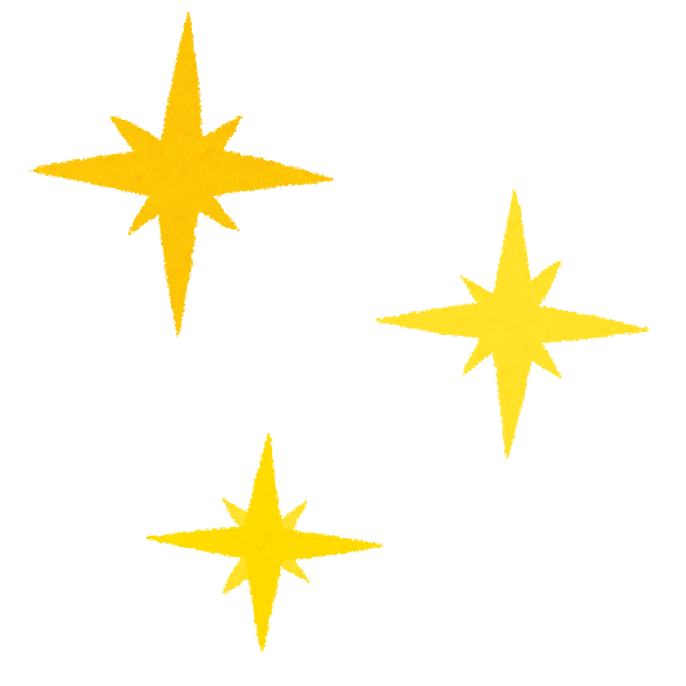 【銀賞】賞金5万円
【銀賞】賞金5万円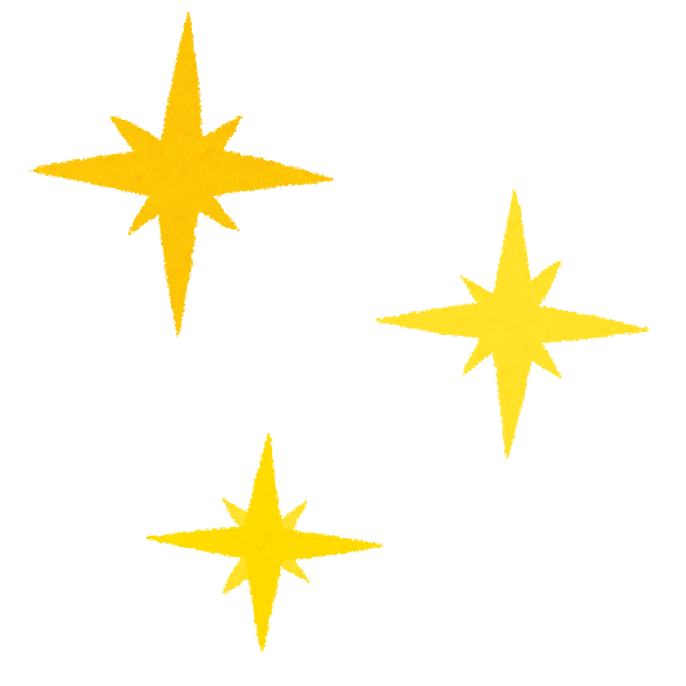
『かすみ荘に暮らす人たち』 ウダ・タマキ
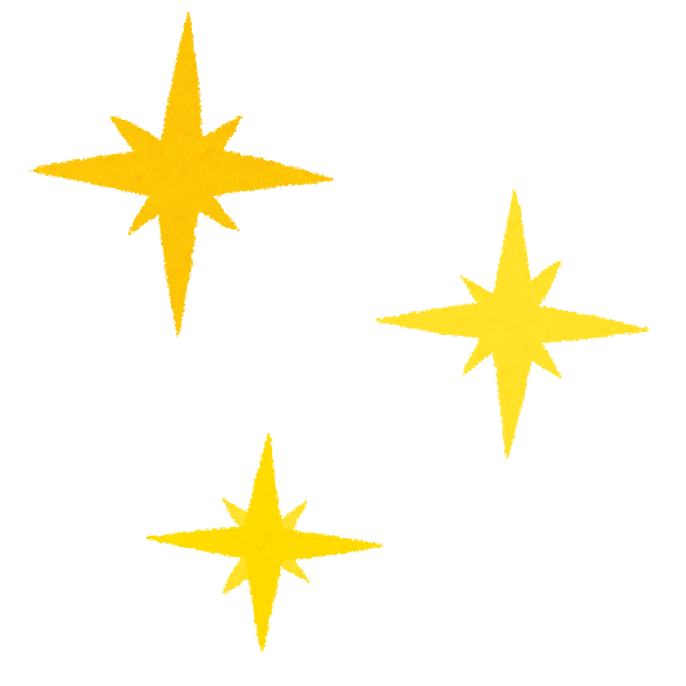 【opsol book賞】賞金1万円
【opsol book賞】賞金1万円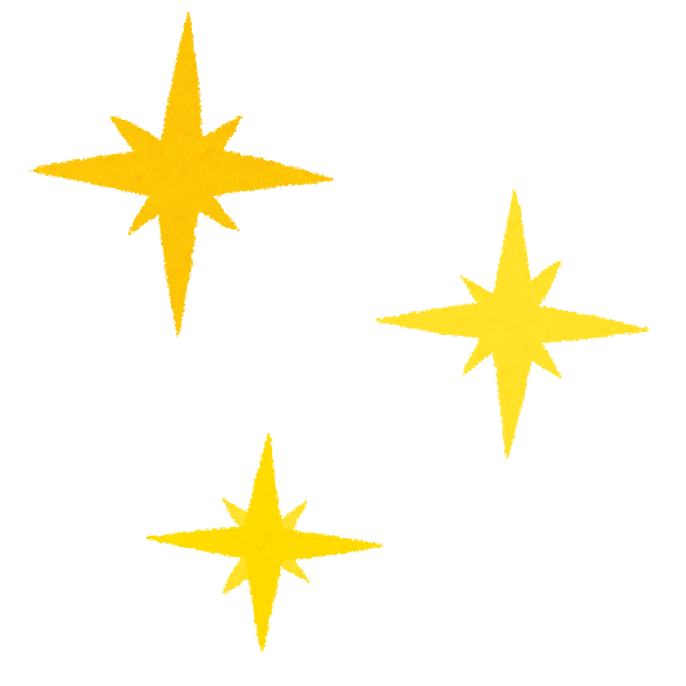
『暁号 国道9号線を爆走中』 本多あにもる
テーマ部門
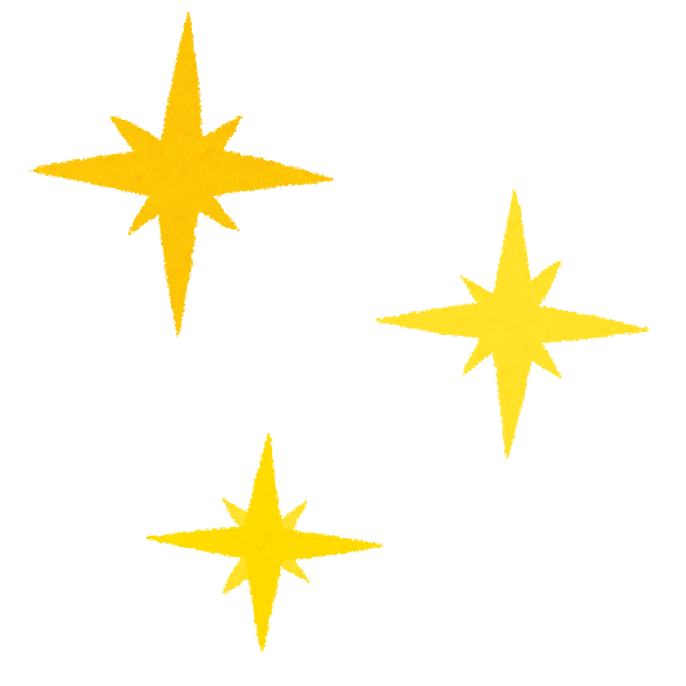 【大賞】賞金30万円+書籍化
【大賞】賞金30万円+書籍化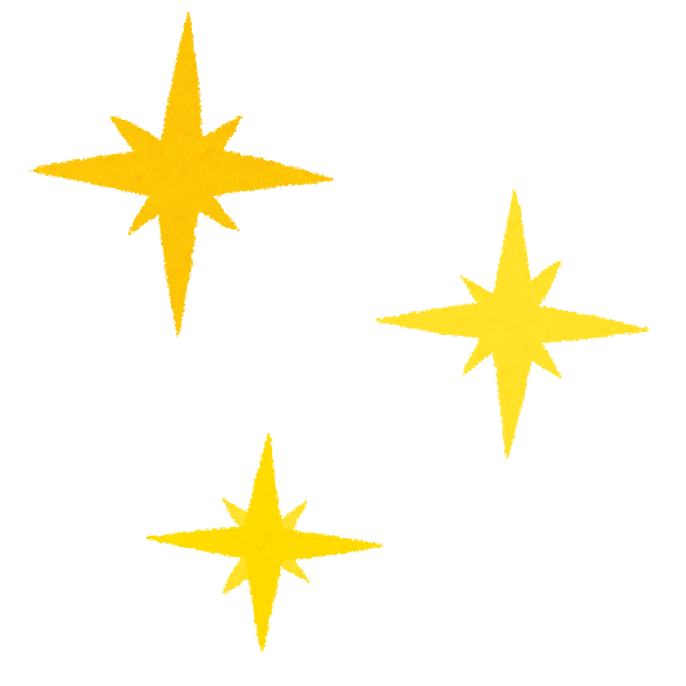
『ハローハロー』 九津十八
【金賞】
該当作品なし
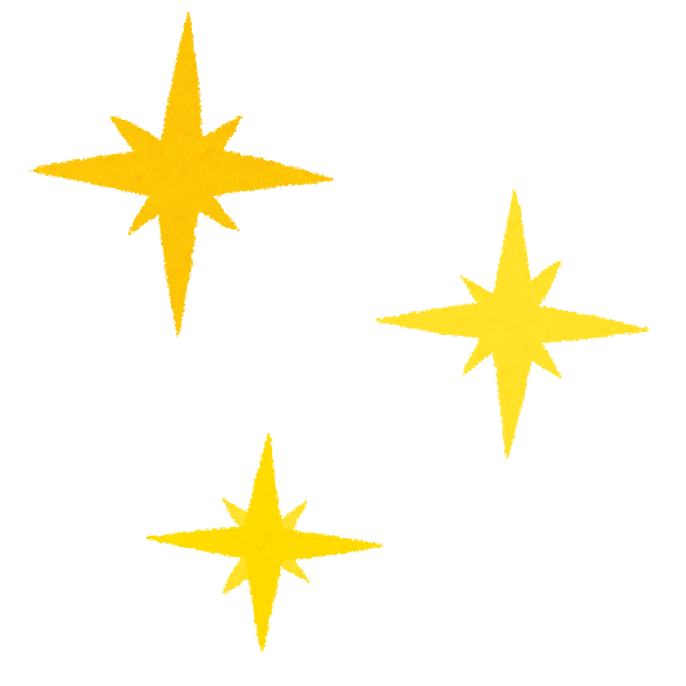 【銀賞】賞金5万円
【銀賞】賞金5万円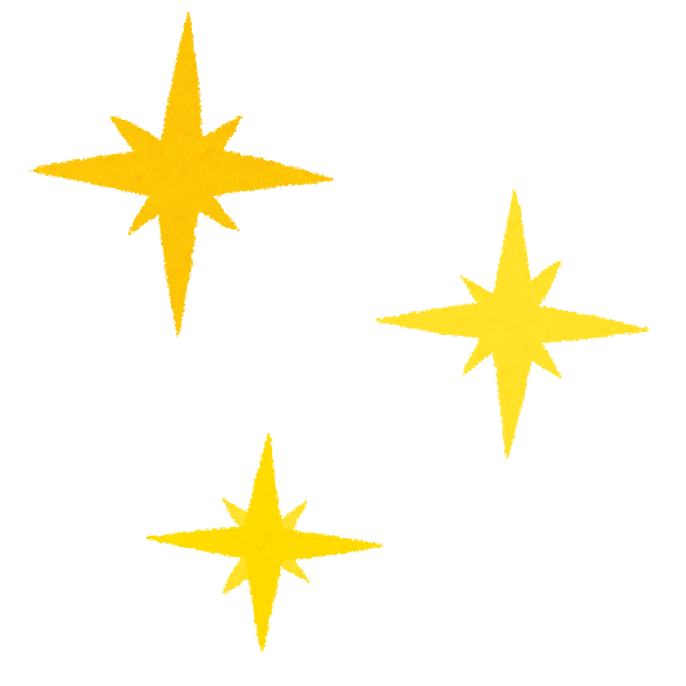
『帰る場所』 目白成樹
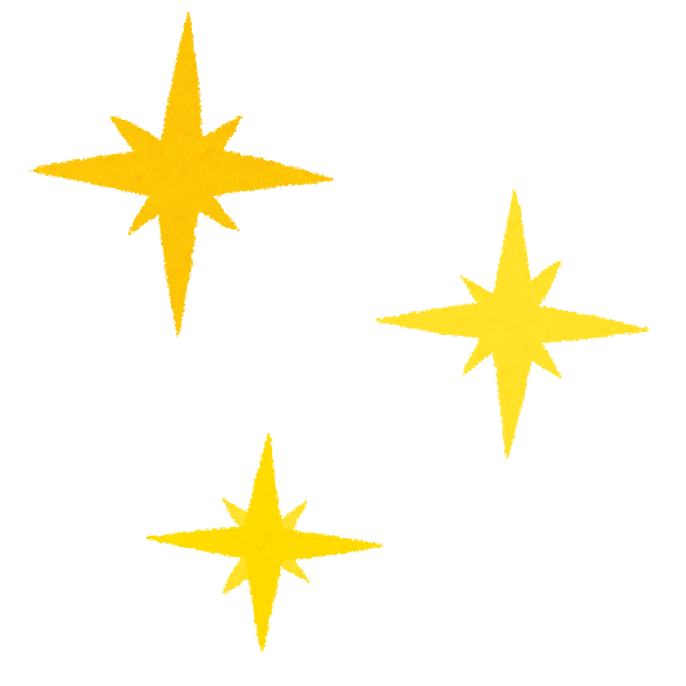 【opsol book賞】賞金1万円
【opsol book賞】賞金1万円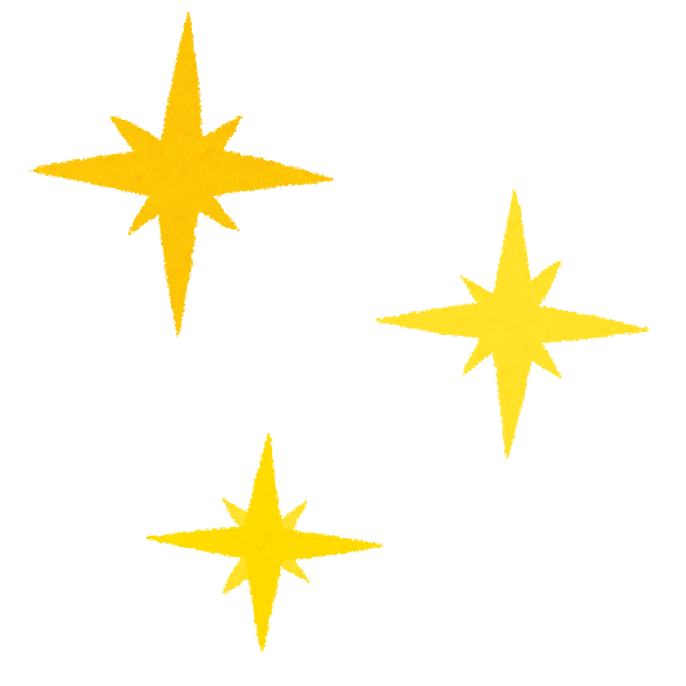
『ぼくとわたしのいるこの世界』 川屋幹大
選評
選考委員
鈴木 征浩【opsol株式会社 代表取締役社長 opsol book代表】
宮川 和夫【装丁家(宮川和夫事務所)】
opsol book編集部
◆opsol部門 大賞『走れ!スーパー茜号』小川マコト(応募時ペンネーム:macoty)
【あらすじ】
今日もあなたに届けるために。茜号、いざ出発!
ハードワークで体調を崩した宮沢祐介は、東京での生活に疲れ、三十歳を前にJターン転職。前職の不動産営業とは打って変わって、緑深い山間の町でお日様のキャラクターが描かれた車を走らせている。転職先のスーパーマーケット「茜屋」では、限界集落や高齢者の一人世帯が多い地域を巡る移動スーパー「茜号」を運営している。祐介はその運転手兼販売員をすることになった。
複雑な家庭環境で育ち家族との縁が薄く、かつての恋人ともうまく付き合えなかった祐介だが、茜号を通じて出会う町の人たちとの交流によって、空虚な心が少しずつ満たされていく。
ある日、常連の千代さんが約束していた商品を買いに来ず、不安を覚える祐介。茜号の利用者は単身の高齢者が多いため、茜屋は地元の自治体と「見守り協定」を結んでいる。千代さんの自宅へ向かい、呼び鈴を鳴らすが反応はない。担当のケアマネジャーに連絡し次の停車地へ向かうも、祐介の嫌な予感は的中し……。
【鈴木 征浩】
スーパーマーケットと行政が「見守り協定」を結び、移動販売員が地域の高齢者の生活を見守る。そこでは、単に「見守る」という行為が実行されるだけではなく、人々の心の交流が生まれ、地域社会が一体となって日々を紡いでいく世界へと繋がっていきます。そして、そのような日々に誠実に向き合えば向き合うほど、たくさんの喜びや奇跡に触れることができる半面で、悲しみや現実にぶつかることも避けることはできません。
本作は、個人的な問題を抱えながらも毎日に真っ直ぐに向き合う青年の毎日を通して、移動販売車が担う役割や見守りの現実を描いています。リズム感の良い文体は時に、社会が抱える問題や避けられない悲しみ、そして主人公の抱える闇にもスポットを当てます。それは根深く、解決の糸口すら見えないものも含まれているのですが、それすらも全て包み込んで毎日時が進んでいくことが、肯定的に描かれています。
章ごとの切り口も良く、ぐんぐん読ませてくれるリーダビリティの高い文章は、物語のテーマを読者に伝えるに際して効果的な役割を担っています。さらに書き込んでもらえれば、と感じる要素もありましたが、総じて高レベルでまとめられており、opsol部門の大賞に相応しい作品であると考えました。
【宮川 和夫】
タイトルがいい。きっと明るいエンタメ小説なのだろうと期待した。
まず、「移動スーパー」「限界集落」「見守り」というモチーフがこの部門賞にあっている。その中で主人公祐介が成長していく姿が清々しい。そしていい意味で、読者がこうあって欲しい方向へと物語が進んでいくのにも好感が持てた。
情景描写の一節の「真っ赤な夕日を背景に、大きな梅の木の枝の下で見送るなみさんの姿が逆光でシルエットのように浮かび上がった」はとてもよく、その後の展開も「こうあって欲しい」内容で映像が浮かんだ。
希望をいえば、特定の地方都市を舞台として欲しかった。地方には「訛り」や「方言」があり、「風習」がある。限界集落ならなおさらだ。それを取り入れることにより、より物語のリアリティが生まれるはずだし、Jターンの祐介との差別化も生まれる。
また、書籍化するには文章量が少なすぎるので、『走れ!スーパー茜号』というシリーズの短編集として、もう一二作書いてみることをお薦めする。
ともあれ、装丁のイメージ、装画(イラストレーション)のイメージも沸き、部門賞の中でダントツに面白い作品だった。
◆opsol部門 銀賞『かすみ荘に暮らす人たち』ウダ・タマキ
【あらすじ】
ケアマネジャーとして、自分にできることとは――?
新人ケアマネジャーの鈴木飛鳥が働く釜ノ崎地域は、かつて日雇い労働者が全国から集う賑やかな街だったが、現在は当時の賑わいを失い、高齢化が著しくなっていた。
そんな街の一角にある「かすみ荘」。面倒見の良い家主・弥生は来るものを拒まない。ここには、複雑な人生を歩んできた高齢者が多く暮らしている。
若年性認知症、末期癌、心と体の性の不一致。さまざまな事情を抱えた住人たちに、ケアマネジャーとして明るく向き合う飛鳥。彼女もまた、苦労の絶えない人生を歩んできた一人だった。そして、かすみ荘に新しく引っ越してきた人物との出会いによって、飛鳥は自分の過去と向き合うこととなる。
【鈴木 征浩】
自身の役割を考え、自身にできることを探して実行していく。新人であるが故に経験値を持たない主人公が、それでも必死に、ケアマネジャーとしての自身の使命を見つけて取り組んでいこうとする姿に、純粋に好感を覚えました。
特に、LGBTQというテーマに触れたエピソードは印象深く、介護・福祉の現場においても改めて認識されてきているテーマを、良い形で物語という形で表現できているな、という印象を受けました。
一方で、新人ケアマネの純粋さを描こうとするあまりに、一部でリアリティに欠けると感じる部分があったことは残念です。物語が必ずしもリアリティのみに溢れている必要などありませんが、現実に目を背けずに向き合うことにより生まれてくる物語や感情は間違いないく存在します。さらに現実と向き合った中で物語を紡ぐことにより、今以上に重厚な作品に生まれ変わることと思います。
そして何よりも、ラストの展開が、あまりにも勿体無く感じました。物語の終わり方というのは非常に難しいものですが、辛抱強く自分自身と向き合い、とことんこだわって物語を結ぶことが、本作をさらなるステージへと導くでしょう。
とはいえ、全体を通して漂っている澄んだ空気感は大変印象的であり、「かすみ荘」という名前とも非常にマッチしています。銀賞に相応しい、伸び代のある作品であると強く感じています。
【宮川 和夫】
優しい予感を感じさせるタイトルがいい。高齢者を受け入れるアパートかすみ荘と、そこに暮らす人々に寄り添う管理人弥生、そしてそこを担当する新人ケアマネの飛鳥という組合せはこの部門賞にぴったりだ。
小川糸さんや瀬尾まいこさんの小説世界を期待しつつ読み進めた。しかし物足りない。というか物語が淡々としすぎていて、最後まで盛り上がらない。いや、別に盛り上がらなくてもいいのだが、かすみ荘に暮らす住人の描写をもっと丁寧にすべきである。その人たちとの関わりの中で飛鳥が成長していく様を見たかった。成長は人の視点を変える。
そして何よりラストが残念。自分を捨てた父親との再会がクライマックスならば、捨てた人間と捨てられた人間、ケアマネとしての自分と素の自分の葛藤をもっともっと描くべきだ。それがこの小説に最も足りない部分であり、それを描くことによって、ようやく柔らかく優しい場所に着地できるのではないだろうか。
◆opsol部門 opsol book賞『暁号 国道9号線を爆走中』本多あにもる
【あらすじ】
暁に向かって、今日も国道9号線を走り続ける。
月森シゲルは、自身のトラックに「暁号」と名前をつけている。トラック運転手であるシゲルにとって暁号は大切な相棒だ。しかし、休憩を終えて駐車場に戻ると、そこに暁号の姿は見当たらない。確かにこの辺りに停めたはずなのに。
新人看護師“ポンちゃん”は、希望していなかった認知症治療病棟に配属となる。なかなか仕事に慣れることができず、先輩にフォローしてもらってばかり。自信を失い、やりがいを感じる余裕もないまま、患者の認知症症状に戸惑う日々を過ごしている。
入院患者の息子・英明は、妻に促されて渋々見舞いに訪れるが、たまにしか病室に顔を出さない自分を、認知症の父は認識できないことがある。英明はそんな状況を未だに受け入れることができず……。
患者、看護師、家族。それぞれの視点で語られる、一人のトラック運転手の物語。
【鈴木 征浩】
認知症の方が生きる世界を描くという手法は目新しいものではないかもしれませんが、当人にとって間違いない現実を描き出すという意味においては、重要な意義を持ちます。認知症の人物とその周囲の人々が、それぞれの立場で見聞きすること、思うこと、を群像劇的に描き出すことにより、認知症というものが抱える現実と、それを取り巻く人々の気持ちが表現された本作は、認知症というものを考えるにあたり、一つのガイドになってくれるかもしれません。
半面、筆力という意味では、課題があると感じました。書きたいことがあるけれど、それを形にしきれていないという印象が強く、ところどころの専門用語も著者の中で噛み砕き切れていないような印象があり、残念に思います。キャラクターごとに地の文の文体を書き分けることができていますので、今後も必ず筆力は上昇すると思います。今後も、さらに読み、書き、を続けていってほしいと願います。
その上で、認知症というテーマについて、ラストに何か展開やまとめのようなものが描かれれば、さらに良い作品に進化していくことと思います。
【宮川 和夫】
タイトル、出だしともよく、期待を持って読んだ。
認知症で入院している月森シゲルは、言葉づかいも含めリアルに描けているが、その他の登場人物があまりに弱く、魅力がない。
シゲルが自分の世界(非現実の世界)を生きる人ならば、新人看護師のポンちゃんや息子の英明の「現実を生きる」人々の葛藤や機微を丁寧に描いて欲しかった。それによってこの物語はもっと深く面白くなると思う。
小説という手法を用いて、認知症という病気を抱える人々に、そしてそれを支える人々に何を伝えたいのか、もう一度考えて欲しい。
◆テーマ部門 大賞『ハローハロー』九津十八
【あらすじ】
僕達は友達じゃない。傍から見ると歪んでいる、二人の関係の名前は――。
中学三年生の加瀬真中は一年生の夏休み以降、登校を拒否している。自己紹介の際に吃音をからかわれ、それからいじめが始まったからだ。
二学期になり、真中の家に車椅子に乗ったクラスメイト・明石京子が訪れた。手渡されたファイルに貼られた付箋には『また学校で会おうね、ピエロ君 カカシより』と書かれていた。彼女の訪問をきっかけに、真中は二年ぶりに学校へ行くことを決心する。
ピエロのように作り笑顔を浮かべて不都合なことをやり過ごしてきた真中と、自身のことを歩けないカカシだと皮肉る京子。互いを見下し合う関係でいることで、心穏やかな学校生活を送らないかと京子に提案され、奇妙な関係を築いていく二人だが……。
【鈴木 征浩】
この輝きはなんでしょうか。
正直に言って、筆力が不足しています。一部の表現には疑問を感じもしますし、矛盾もあると思います。
しかしながら、本作には、著者の書きたいことが、書きたいという思いが、目一杯詰まっており、収まり切らずに溢れ出てしまっています。有無を言わさない物語の力。読み終えた時、心は喜びで満たされていました。
吃音、そして車椅子という、日常に確かにあるけれど、全く簡単ではないテーマ。それらを中学生の男女ふたりを通して描き、現実的な問題を描きながらも、そんな問題の中で、なんとか毎日を生きている彼らが出会いと交流を通して徐々に「生きている」から「生きようとする」姿へと変化していく物語。思春期の心は敏感で、すぐに壊れてしまいそうにもなりますが、時に驚くほどに強くしなやかに、現実を切り開いていきます。
彼らが選んだ結末は、「彼ら以外」にとっては忌むべきものかもしれません。しかし、それは彼らの人生の心の叫びなのです。そして「彼ら以外」に、意識せず読者自身が含まれてしまっていないと言えるでしょうか? そんな問いもまた、突きつけられます。
荒削りではありますが確かな輝きに満ちた本作は、テーマ部門大賞に相応しい作品だと確信しています。
【宮川 和夫】
「あの人は自分よりもかわいそうだから……」
自分よりも不幸な人のことを想像して安心する。そういう人は多いと思う。
「吃音」の主人公、加瀬真中と「車椅子」の明石京子は、「ピエロ」と「カカシ」という比喩を用い、互いを見下す相手としつつ、寄り添う相手として意識する。
出だしから心が苦しくなった。それはこの物語が、「お前はこの『ふたり』を本当に受け入れることができるのか」と問うているからだ。
物語は、中学校という閉ざされた空間、思春期の子どもたちの残酷さ、教師という絶対権力者、学校というある種世間と乖離した世界での人の無意識的無慈悲さの中で展開する。これは、誰もが理解できる世界で空間設定としていい。
この物語の中で、私が意表を突かれ、かつとてもよいと思ったのは、修学旅行先の長崎でラブホテルに入るという場面だ。障害を抱えているとはいえ、思春期の男女だからなと、げすな大人(僕のことですが)は想像するのだが、そうではなくそこからエンディングに向けて物語は加速していく。無理解な生活指導教師との対峙から卒業式のドラマティックなシーンへの展開は圧巻だった。
装丁家として作品を読むときに意識しているのは、登場人物が見えるかどうかだが、この作品の真中と京子は確かに目前に現れた。そしてこのふたりを描く装画家(イラストレーター)はこの人だとも思った。
ところで、文中のふたりの合い言葉「ハロハロ」はフィリピンのタガログ語の「まぜこぜ」を意識したのではないか。どんな人も差別なく自由に生きられる社会、すなわち「多様性」を考えた言葉とかけたと思うのは考えすぎだろうか。
◆テーマ部門 銀賞『帰る場所』目白成樹
【あらすじ】
それぞれが抱えた過去を胸に、二人の男は小説を書き続ける。
主人公の“私”は定年退職後、小説講座に通い始める。七年前に自死した部下のことが頭から離れず、友人から小説にでも書いたらどうだと勧められたのだ。
その講座で出会ったN氏は、明治から続く貿易会社の代表者で、引退後にその一族の歴史を小説に書いているのだと言う。
親交が深まったと感じても、なぜかN氏は急に冷たくなるときがある。自分はあなたとは違い、楽しんで小説を書いているわけではないのだと言い放つことも。私は、自分がそうであるように、彼もまた心を許してくれていると、そう思っていたのだが……。
どうして部下は死んだのか。N氏の態度の理由とは。彼らが執筆を終えたとき、真実が明らかになる。
【鈴木 征浩】
様々な「ふたり」が描かれた作品たちの中で、人生の第1ステージを終えた男性ふたりによる物語という設定は、目を惹かれるものがありました。また、そのふたりが、元から友人同士や知人同士ということではなく、小説講座で出会い交流を重ねていくという物語にも、惹かれるものがありました。
淡々と描かれる物語ですが、それぞれに重いものを抱えている主人公たちを、文体がうまく表現しているように感じます。どんどん読み進めることができる物語のクライマックスに登場する「N氏」の「手紙」は素晴らしい内容でした。
ただ、物語全体を通して見たときに、中盤の展開の一部が本当に必要だったのか、あるいは、中盤の展開で描こうとしていたものがしっかりと描かれていたか、という点では、引っ掛かりを覚えました。最初の部分と最後の部分には共通して流れているものをしっかりと感じることができるからこそ、どうしても中盤の部分に違和感を感じてまったのが残念です。また、タイトルに重要な意味を感じるからこそ、それについても描ききれていないように感じてしまいました。
とはいえ、確かな魅力を感じる作品です。作中で表現したいことを一本の繋がりとして意識されることで、さらに良い作品になることと思います。
【宮川 和夫】
大変筆力のある方であるのは確かだが、主人公の気持ちにもN氏の心情にも今ひとつ入り込めなかった。それはこの物語の匿名性がどうしても気になったからだ。
主人公は小説講座を通じてN氏と知り合い、シンパシーを感じ、早稲田大学の村上春樹ライブラリーや東京都美術館だと思うが、一緒に行くシーンは淡々としていすぎて何故このシーンが必要なのか理解できなかった。しかし、気がつくとN氏への連絡先を一切知らなかった(知る気がなかった)主人公の性格、人との距離の取り方が分かっていくにつれ納得もした。
主人公の部下の自死とN氏の婦人の死、そしてN氏自身の自死を予感させる手紙をどこかで結びつけ収束するかと思ったのだが、最後まで何も解決されないままだった。確かにこれも一つの純文学の手法だろうし、現実とはこういうものだとも思うが、漂う暗さ、登場人物が皆下を向いて生きている様は最後まで辛かった。短編集の中の一作として見ればいいかもしれない。
◆テーマ部門 opsol book賞『ぼくとわたしのいるこの世界』川屋幹大
【あらすじ】
ぼくはあと四日でこの世を去るらしい。その未来を、彼女は知らない。
ある日突然現れた男によって、四日後の死を宣告された枕崎雄馬。恋人の鬼塚楓に相談するも、楓は雄馬から受けた相談を数秒で忘れてしまう。どうやら、自身の死を周りにいくら打ち明けても、相手は何も理解できないらしい。代わりに、死ぬまでに一つだけ何でも願い事を叶えてあげると男は言う。
自身の死を匂わせる言葉は残すことができない。楓の幸せを保証してもらうこともできない。彼女に残せるものが何もないと諦めかけたとき、思い出したのは一つの花の名。二人の人生が交差したあの日、彼女が教えてくれた「アングレカム」。多くの制約がある中で、雄馬は最後に何を願うのか。
一組の男女が時を越えて心を通じ合わせる、環世界を巡るラブストーリー。
【鈴木 征浩】
主人公をはじめ、登場人物の個性が良く現れており、それぞれがキャラクターとして活き活きと描かれていたことが印象的です。設定も面白く、独自の視点が織り込まれた物語は、最後まで、興味を持って読むことができました。
審査において最大のポイントとなったのは、そのテーマ性についてです。本部門のテーマは『ふたり』ですが、残念ながら、物語の中で強くその言葉を意識することができませんでした。確かに、主人公とそれぞれの登場人物、という、「ふたり性」とでも言おう要素がなかったというわけではありませんが、他の授賞候補作が「ふたり」をしっかりと意識させてくれるものであったのと比べると、どうしても印象が薄くなってしまいました。
あくまでも本賞に限っての話であり、作品そのものの評価云々ではありませんが、「ふたり」というテーマをもっと強く意識して書かれていたらどうなっていただろう、という感情が残る結果となりました。
【宮川 和夫】
あらすじを読んだときに、ああよくある設定か、と思った。しかし、読み進めるにつれ作品の世界に引き込まれていった。応募作品の中で一番読ませる力のある作品だと思ったが、テーマの「ふたり」からすると、登場人物の関わりの多さからふたりに絞りきれない点が気になった。
作中に用いられるキーワード「環世界」、またそれを唱えるドイツの生物学者であり哲学者のユクスキュルのことを知らなかったので、急いで調べてみた。「生物は自分自身が持つ知覚によってのみ世界を理解しているので、全ての生物にとって世界は客観的な環境ではなく、生物各々が主体的に構築する独自の世界である」というのが「環世界」の考え方らしい。なるほど、実は私も常々そう考えていた。例えば蜂や蝶のみに見える周波数の色とか、犬のみに知覚できる臭いとか。また「アングレカム」という花も効果的に使われている。
登場人物の描写が素晴らしく、血肉のある人が描けていると思った。私の中では一押しであった。
大賞受賞者 受賞コメント(2024/2/26 更新)
◆opsol部門 大賞 『走れ!スーパー茜号』小川マコト(応募時ペンネーム:macoty)
〈受賞コメント〉
TVの脚本を書いていた時、苦しかった事の一つが母性や家族を否定的に描けない事でした。
スポンサーの広告費によって制作される構造上「家族とは尊いもの」というベタな家族神話は否定し辛い。
母性神話も然り。
しかし、その神話が苛烈な環境下に生まれ育った人々をより追い詰めるのではないか、否定こそ彼らにとって光なのではないかと祈るような思いで書きました。
この否定の物語を肯定して大賞に選んで下さり感謝申し上げます。〈著者プロフィール〉
TVアニメ、TVドラマの脚本家を経て現在、コミックの原作に従事。
企画ユニットcarousel キャラセル(X@7sevenSegment) に参加。
旅が生き甲斐。
◆テーマ部門 大賞 『ハローハロー』九津十八
〈受賞コメント〉
この作品を書き上げた時、どの賞に送ろうか迷っていたところにあまりに作品のテーマとぴったりな賞があるぞと応募しました。
私が中学三年生の時に一年生で車椅子の女子が入学してきました。二つ下ということで名前も知らなかったのですが、ある日、少しの段差で手こずっているのを見かけました。
しかし、思春期ということもあってか、恥ずかしいという気持ちが勝り、手助けをしなかったことを、今でも心の奥に刺さる棘としてずっと残っています。
この物語はその棘をどうしても抜きたくて書き始めました。書き上げたことで棘が抜けたかと言われると、未だに抜けていません。
しかし、今回の結果を受けてこれから先、この痛みともっと真っ直ぐに向きあおう。そう思えるようになりました。
最後になりますが、大賞という結果をいただき大変光栄です。〈著者プロフィール〉
1987年生まれ。兵庫県加古川市出身。野球観戦とゲーム配信視聴が趣味。
総評
確かな意義を感じながらも不安の中でスタートしたハナショウブ小説賞ですが、第1回の興奮も冷めやらぬ中開催した第2回にも、数多くのご応募を頂戴できましたこと、大変光栄に思いますとともに、皆様に厚く御礼申し上げます。
第2回においては、「介護・医療・福祉」をテーマとしたものを『opsol部門』として整理すると同時に、新たに『テーマ部門』を設け、今回は「ふたり」というテーマを設定させていただきました。
opsol部門には、介護・医療・福祉という限定的なテーマながら、様々な切り口の作品にご応募いただきました。特に介護や福祉というものは、小説作品に昇華させることが難しい側面がある中で、様々な角度からチャレンジしていただくことができたことは、主催者として大きな喜びです。
そしてテーマ部門においては、実に様々な「ふたり」にご応募いただくだくことができました。身近な「ふたり」だけでなく、存在、概念、象徴、そいうった様々な「ふたり」の物語は、発見に溢れていました。
そのような作品と向き合う中で今回強く考えたのは、「物語を終えることの難しさ」についてです。
書きたい何かがある、書きたい物語がある、そいういった時、著者はエネルギーに満ち満ちていて、溢れる想いを必死に文章に落とし込んでいくことと思います。しかしながら、物語を本当の意味で成立させ、第三者が読める形で、第三者に届く形で、作品としてまとめ上げるためには、きちんとした形で物語を締め括らなければなりません。それは至難の業であり、応募作品の中でも、どうしてもラストが物足りない、形になっていない、まとまっていない、と感じるものがいくつもありました。そして、だからこそ、たとえ不完全であったとしても、ラストの一文字までしっかりと向き合って書かれたであろう作品からは、特別な力を感じ、また、心から敬意を覚えることができました。
物語を最後までしっかりと形にする作業は困難を極めますが、せっかく情熱を持って小説を書いていただくのですから、ぜひ最後の最後まで自身の作品と向き合っていただけたらと思います。それはきっと苦しみの連続ですが、その先には間違いなく、新たな地平が広がっています。
第1回に続いて、皆様の大切な作品をお預けいただけましたこと、心より光栄に思います。
そして、今回も書籍化に相応しい作品に授賞させていただけますことを、本当に嬉しく思います。
サイクルは変わりますが、第3回ハナショウブ小説賞も開催いたしますので、引き続きご愛顧いただけましたら幸甚に存じます。
2024年1月31日
opsol株式会社 代表取締役社長
opsol book代表 鈴木 征浩
三重県伊勢市小俣町の出版社
オプソルブック
opsol book
(opsol株式会社 opsol book事業本部)
〒519-0503
三重県伊勢市小俣町元町623番1
TEL:0596-28-3906
FAX:0596-28-7766